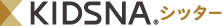保育参観に下の子を連れて行く?園への確認事項や注意点、当日の預け先

【体験談】保育参観に下の子を連れて行く?
 Sally B / stock.adobe.com
Sally B / stock.adobe.com
上の子が保育園や幼稚園に通っている家庭では、保育参観をはじめ、さまざまな園行事に参加する機会がたくさんありますよね。そのたびに、下の子を連れて行くべきか、どうすればよいのかと悩むママやパパも多いのではないでしょうか。
ここではまず、保育園や幼稚園の保育参観に出席するとき、下の子を連れて行ったかどうかをママやパパに聞いてみました。
連れて行った
下の子がぐずり出したらすぐに退出できるように、出入り口の近くで参観したママや、下の子がすごしやすいよう持ち物を意識したママがいました。ドア付近のスペースが空いていない場合は、あらかじめ教室の外に出て、廊下側から上の子を見守ってもよいかもしれません。
連れて行かなかった
参観中に下の子が周囲に迷惑をかけるかもしれないという理由で、保育参観に連れて行かない方もいるようです。誰かに預けることができれば、下の子もお昼寝や遊びといった生活リズムを崩さずにすごせるかもしれません。
以下の記事では、親子遠足や卒園式といった園の行事での下の子の対応法を紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
保育参観に下の子を連れて行くか迷ったときに確認すること
 polkadot / stock.adobe.com
polkadot / stock.adobe.com
保育参観に行く場合、事前にどのようなことを保育園や幼稚園に確認するとよいのでしょう。あらかじめ確認しておくことで、下の子を連れて行くかどうかの判断材料にもなるかもしれません。
実際に確認したことをママやパパに聞いてみました。
参観の内容
参観の内容によっては、上の子とふたりだけで活動したいと考えるパパもいるようです。ほかにも、親子スポーツのように上の子とふたりで体を動かして楽しむ活動もあるようなので、内容を確認してから下の子を連れて行くかどうか決めているというママの声もありました。
園のルール
園によっては保育参観に保護者だけで参加してほしいというルールを設けている場合があるかもしれません。預け先を探すことを考えて、参観や行事の際は下の子の参加が認められているかを早めに確認したというママの声もありました。
保育参観に下の子を連れて行く場合の注意点
 yamasan / stock.adobe.com
yamasan / stock.adobe.com
参観内容や園のルールを確認したうえで、やむを得ず下の子を連れて行くことになった場合、どのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。
保育参観に下の子を同伴する際の注意点を、ママたちの体験談をもとにまとめました。
保護者席の隅や後列に座る
下の子がぐずり出したときにすぐに席を立てるよう、保護者席の通路側や後列に座るよう心がけているママは多いようです。このちょっとした工夫で、周りに配慮しつつ、上の子の様子を落ち着いて見守ることができるかもしれません。また、いつでも席を立てるという心の余裕が生まれ、ママやパパ自身の負担も軽減されるでしょう。参観当日は、下の子のお気に入りのおもちゃやお菓子をいくつか持参し、子どもが退屈しないように工夫するのもよいかもしれません。
ぐずり始めたら退室する
下の子がぐずり始めたらすぐに教室から退室することも大切でしょう。参観途中で退室しても、廊下の窓から見守る、落ち着いたら再び入室するなど、方法はいくつかあるようです。柔軟な対応が、上の子も下の子も、そしてママやパパ自身も安心してすごすカギかもしれません。
下の子から目を離さない
参観時は、上の子の様子に夢中になりがちですが、下の子から決して目を離さないように注意しましょう。特に歩き回れる年齢の子の場合、好奇心から思わぬ行動に出てしまうことがあるかもしれません。上の子の様子を見守りながら、下の子を常に自分の視界の範囲内に入れておくように心がけているというパパの声も聞かれました。
育児アイテムの準備を万全にしておく
下の子が快適にすごせるように育児アイテムを万全に準備しておくことが大切なようです。なかには、いつも持ち歩いているお気に入りのおもちゃを準備しておくと、場所見知りや人見知りを緩和してくれるという声も聞かれました。
保育参観当日の下の子の預け先
 ucchie79 / stock.adobe.com
ucchie79 / stock.adobe.com
一方で、下の子を預けて親だけで保育参観に参加するという方もいるでしょう。保育参観当日の下の子の預け先について、ママやパパたちに聞いてみました。
両親やパートナー
参観日の下の子の預け先として、実家の両親にお願いしているママがいました。ほかにも、夫婦どちらの実家も遠方にあるため、参観日当日はパパが仕事を休んで子どもと留守番をしているというママの声もありました。両親やパートナーは下の子の預け先として、もっとも安心できる存在かもしれません。
民間の託児所
自宅の近くに民間の託児所がある場合は、保育参観当日の下の子の預け先として利用するのもよいかもしれません。事前に会員登録が必要な託児所もあるようなので、早めに確認しておくとよいでしょう。
ファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポート・センターは、子育てのサポートを必要とする人と、子育て支援をしたい人が会員となり、お互いに助け合う事業です。地域の子育て経験者がサポートしてくれるため、安心して預けられるのが大きなメリットでしょう。事前登録が必要な場合が多いため、利用を検討する際は自治体へ早めに問い合わせてみましょう。
ベビーシッターサービス
ベビーシッターサービスを定期的に利用していると、保育参観当日にも子どもをスムーズに預けられそうです。ママのなかには、自宅でシッティングをしてもらえるので、出かけるときの準備が簡単にできてありがたいという声もありました。
保育参観への下の子同伴に関するよくある質問
保育参観に下の子を連れて行くかどうか悩んでいるママやパパのために、よくある質問とその答えをまとめました。
Q1.下の子がぐずったり泣き出したりしてしまったらどうすればいい?
A.下の子がぐずったり泣き出したりしてしまっても、決して焦らないようにしましょう。子どもが泣くのはごく自然なことです。まずは、ママやパパ自身が落ち着いて、一度会場から出て気分転換をさせてあげましょう。廊下を少し歩いたり静かな場所で抱っこしたりするだけで、落ち着くかもしれません。また、子どもが好きな絵本やおもちゃを持参しておくと、いざというときに役立ちます。
Q2.授乳やオムツ替えの場所はある?
A.園によって対応はさまざまですが、授乳やオムツ替えができる場所を用意してくれている施設もあるようです。しかし、スペースが限られている場合や、そもそも設けていない場合もあるため、心配な場合は事前に園に確認しておきましょう。もしそのような場所がない場合でも、授乳ケープや携帯用のオムツ替えシートを持参しておけば、臨機応変に対応できるかもしれません。
Q3.下の子を連れて行くことで上の子に悪影響はない?
A.下の子に手を取られてしまい、上の子との時間が減ってしまうのではないかと心配になるママやパパもいるかもしれません。しかし、もっとも大切なのは上の子の頑張りをたくさん褒めてあげることでしょう。保育参観後、上の子に「〇〇ちゃん、歌をじょうずに歌えていてすごいね!」などと声をかけてあげたり、自宅で参観中の様子を写真や動画で見返しながら、ゆっくり話す時間をもったりするとよいかもしれません。そうすることで、愛情を伝えることができるのではないでしょうか。
Q4.下の子の預け先はどうやって探せばいい?
A.下の子の預け先は、一時預かりに対応している保育園や、地域の子育て経験者がお手伝いしてくれるファミリー・サポート・センター、自宅で預かってもらえるベビーシッターサービスなど、さまざまあります。それぞれのサービスの特徴や料金を比較検討し、ご家庭に合った方法を見つけてみてください。
Q5.いつまでに預け先を確保すればいい?
A.保育参観の日程がわかったら、できるだけ早く預け先を探し始めましょう。特に、人気のサービスや施設は、すぐに予約が埋まってしまうことも考えられます。ママたちの体験談によると、少なくとも1カ月前までには予約を完了させておくと安心なようです。早めに動いておくことで、選択肢も増え、気持ちにも余裕が生まれるでしょう。
Q6.預け先によってどのくらいの費用がかかる?
A.費用は預け先によって大きく異なります。ファミリー・サポート・センターは、利用料金が比較的安価だといわれています。一方でベビーシッターサービスは、時間帯やシッターさんの経験によって料金が変わることもあり、高価なイメージをお持ちの方も多いでしょう。しかし企業型ベビーシッター割引券や自治体による助成制度を活用できる場合もあるため、実際には身近なサービスとして気軽に利用できるかもしれません。また、利用料金だけでなく、施設の雰囲気やサービス内容も考慮して決めるようにしましょう。
以下の記事では、託児所や一時預かり保育、ベビーシッターサービスの料金相場を紹介しています。比較検討する際の参考にしてみてください。
保育参観当日は下の子を預けることも選択肢に
保育参観に下の子を連れて行く場合は、子どもにも周りにも負担や迷惑のないようにと考えているママやパパが多いようです。一方で、上の子の様子をしっかり見守りたかったり、参観内容や園のルールによって下の子を連れて行けなかったりする場合は、子どもがのびのびとすごせる預け先を探してみましょう。ベビーシッターサービスやファミリー・サポート・センター、一時預かり事業などをじょうずに活用することで、下の子も楽しく遊びながらママやパパの帰りを待てるかもしれません。
保育参観に行くときには、上の子も下の子も気持ちよくすごせるように、それぞれの家庭にあった方法で工夫できるとよいですね。
保育参観日に下の子を預けるなら「キズナシッター」の活用を
子どもの預かり先を探す家庭のなかには「保育参観に出席するために下の子を預かってもらいたい」「家族に預けられないのでベビーシッターサービスを利用したい」というシーンもあるかもしれません。
そんなときは「キズナシッター」の利用を考えてみてはいかがでしょうか。
キズナシッターは、0歳の赤ちゃんから12歳の子どもまでを対象としたベビーシッターサービスです。登録しているベビーシッター全員が、保育士や幼稚園教諭、看護師などの国家資格を所有しています。前日の利用予約にも対応できるため、仕事などで急な用事ができたときの子どもの預かり先としても活用しやすいと好評です。
一時利用のほかに、子どもが慣れているベビーシッターの方への定期利用も可能なため、保育園や幼稚園へ入園が決まるまでの期間に利用している家庭も少なくありません。園でのさまざまな行事やイベントの際に、信頼できるシッターさんに下の子をお願いできるというママたちの声も届いています。
いざというときの子どもの預け先として、この機会にぜひ、キズナシッターの会員登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらKIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。