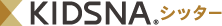訪問型のベビーシッターと自宅で預かる保育ママ。在宅保育の業務内容と特徴、開業準備

在宅保育の「ベビーシッター」と「保育ママ」
保育園などの施設で行う保育に対して、保育者や保護者の居宅などで子どもを預かり保育することを「在宅保育」と言います。
在宅保育のなかには、主にふたつの種類があります。
保護者の自宅に行き保育を行なう「ベビーシッター」と、保育者の自宅で保育を行う「保育ママ」(家庭的保育)です。
このふたつの在宅保育は、個人でも開業することが可能なため、「保育園の人間関係から離れて、自分の理想とする保育をしたい」「個別保育をもっとていねいにしていきたい」「保護者をよりサポートしていきたい」と考える方にとってぴったりな働き方かもしれません。
それぞれの特徴を知り、より自分が理想とする在宅保育を見つけていきましょう。
訪問型の在宅保育サービス「ベビーシッター」
 maroke / stock.adobe.com
maroke / stock.adobe.com
ベビーシッターは、主に利用者の自宅に行き、保護者の代わりとなって子どもの保育やお世話を行います。
最近では、「働いている間だけ」「短時間の用事の間だけ」など、保護者のニーズに合わせた多様な理由でベビーシッターが利用されています。また、そのような便利さから、利用者も増えつつあるようです。
ベビーシッターは、パートやアルバイトとして働く方が多い一方で、マッチングサービスや自身のウェブサイト、SNSなどを活用しながらフリーランスで働いている方も増えています。個人のスキルや経験を活かして自由に働きたいというニーズの高まりを反映しているのかもしれません。
仕事内容
主な仕事内容は、利用者の自宅に行き、子どもの保育や世話を行うことです。
対象となるのは、おおむね0歳から12歳と幅広いため、具体的な仕事内容は、それぞれのお子さまの年齢や発達、家庭の要望に応じて異なってくるでしょう。
基本的にはマンツーマンの保育になりますが、きょうだいなど一度に複数人の保育を行うこともあります。さらに、室内保育のほかにも、幼稚園や習い事への送迎など、提供するサービスによって、自宅以外に出向くこともあるのが特徴でしょう。
開業するには
ベビーシッターとして仕事を始めるには、お住まいの自治体に届け出を提出する必要があります。また、利用者の募集を自分で行わなければいけないことも忘れてはいけない点です。
一方で、利用者とベビーシッターを結びつける「マッチングサービス」を利用したり、ベビーシッター専用の派遣社員になったりすることで、スムーズな集客を図る方法もあります。
特徴
ベビーシッターは、利用者の自宅で預かる保育になるため、子どもが慣れ親しんだ環境でシッティングできることが大きな特徴といえるでしょう。たとえば、子どもが普段遊んでいるおもちゃを使ったり、事前の打ち合わせで好きな遊びを聞いておき、それに合わせた遊びを提案したりすることで、子どもがより安心してすごすことができるよう配慮します。子どもとの関わりは、ほとんどの場合マンツーマンとなるため、子どもの思いを大切にしながら、ていねいな保育ができることも魅力かもしれません。
働き方としては、短時間からの勤務が可能なため、時間の融通がききやすく、家庭をもっている方や子育て中の方にとっては、仕事と家庭のバランスを保ちながら仕事ができるようです。
その一方で、子どもの保育をひとりで行うため、責任がある仕事ともいえます。子どものケガなど万が一のときのために、保険に加入できるような働き方を調べておくことが大切でしょう。
ベビーシッターは、利用者がリピーターとなるケースもあるようですが、基本的には毎回保育をする家庭が変わります。子どもや保護者との関係づくりが必要になる分、臨機応変な対応力も重要になってくるでしょう。
保育者の自宅で預かる「保育ママ」
 ucchie79 / stock.adobe.com
ucchie79 / stock.adobe.com
保育ママとは保育者の家が園舎となる、もっとも規模が小さい保育園のかたちです。
自治体の認定を受けており、市区町村によって「家庭的保育者」「保育ママ」などといった名称や、具体的な制度内容もそれぞれ異なります。
この保育ママ制度は、2010年の児童福祉法改定により、保育サービスの普及促進や子育て支援の充実のために「家庭的保育事業」として始まったものです。この制度は、全国で行われているわけではなく、自治体によっては実施していない場合もあるようです。
そのため、保育ママを目指す場合には、まず自治体の制度を確認することが必要になるでしょう。
出典:児童福祉法等の一部を改正する法律案概要/厚生労働省仕事内容
保育ママの主な仕事は、少人数の子どもを自宅で預かり、家庭的な雰囲気のなかで保育を行うことです。
ひとりの保育ママが預かる子どもの人数は、3歳未満児の3人までとされていますが、いっしょに働く保育者などがいる場合は、最大5人まで預かることができると定められています。ただし、このような国が定める基準に加えて、各自治体が独自の条例で詳細な基準を定めている場合もあるようです。
日々の保育方針や保育内容については、保育ママが決めることができるため、子どもの発達やその日の様子に応じて、臨機応変に対応していくことが重要でしょう。
出典:家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準/厚生労働省開業するためには
保育ママとして開業するには、自治体の認定を受けるための条件を満たす必要があります。なかには、本人の資格の有無や年齢、未就学児を育児中ではないかなどの条件を細かく定めている自治体もあるようです。
たとえば、そのような条件のひとつに、保育場所の確保があります。
保育ママは、基本的に子どもを自宅で預かることができる場所を準備しなければならないため、各自治体が提示する条件に合わせて、自宅に保育用のスペースを確保したり、場合によっては、リフォームや改修工事が必要になったりすることもあるでしょう。また、保育スペースの準備のほかにも、役所に提出する書類の作成や研修に参加する必要もあるようです。
なお、利用者の募集は自治体が行うため、保育ママ自身が募集活動を行う必要はほとんどないでしょう。
特徴
保育ママとして働く場合、かなり少人数の保育となるため、そのような家庭的な環境のなかで、きめ細やかな保育ができることが大きな特徴といえるでしょう。
対象となる子どもの年齢は、成長に個人差が大きい0歳~2歳児が中心となります。一人ひとりの発達や個性、その日の様子に応じて、環境や活動を工夫し、子どもにとってすごしやすい環境を作っていくことができるでしょう。
さらに、保護者との距離が近いことで、日々の子どもの成長をともに共有できることも魅力のようです。少人数保育の利点を生かし、体調の変化はもちろん、そのほかの小さな変化を見逃さないことが大切かもしれません。
働くうえでは、勤務地が基本的に自宅になることから、通勤の負担がなく、その時間を保育の準備や子どもの迎え入れに充てることができ、より業務に集中できることが挙げられるでしょう。また、保育ママは自治体から認定される公的な制度のため、補助金を受けることができます。自治体によっては、保育ママのスキルアップ研修や近隣の保育園との連携など、さまざまなサポートも用意されているようです。
その一方で、開業するまでの役所への手続きや、保育場所の確保の負担、会計管理や協力してくれる保育者の確保など、自分でやらなければならないことが多いことも特徴として挙げられるでしょう。
在宅保育に関するよくある質問
ベビーシッターと保育ママのふたつの在宅保育について紹介してきましたが、これからこのような事業を始めたいと考える方にとって参考になるような質問と答えをまとめました。子どもを自宅で預かる働き方について考える際のヒントにしてみてください。
Q1.在宅保育を開業するために、特別な資格は必要?
A.ベビーシッターと保育ママとでは、必要な資格が異なります。
ベビーシッター
基本的に開業に必須となる公的な資格はありません。しかし、専門的な知識やスキルを証明するために、公益社団法人全国保育サービス協会が認定する「認定ベビーシッター」のような民間資格があります。こうした資格は、保護者からの信頼を得るうえで有効でしょう。
保育ママ
自治体の認可事業であり、統一された資格はありませんが、多くの場合、保育士や幼稚園教諭、看護師などの国家資格が必須とされています。自治体によっては、子育て支援員研修の修了が必要となる場合があるようです。
以下の記事では、ベビーシッターに必要な資格について詳しく紹介しています。自分に合ったベビーシッター資格を見つけてみましょう。
Q2.自宅で預かるスペースを作るには、条件がある?
A.自治体によって詳細は異なるものの、いくつかの条件があるようです。
保育室の広さや安全性、衛生環境などについて、子どもを自宅で預かるために各自治体が定めた基準を満たす必要があります。具体的には、採光や換気、子どもの安全を確保するための設備(家具の転倒防止など)が求められるようです。
Q3.開業後、集客や利用者の募集はどうすればいい?
A.集客方法は、ベビーシッターと保育ママとで大きく異なります。
ベビーシッター:個人事業主として活動するため、自分で集客を行う必要があります
主な方法には以下のものがあります。
- ベビーシッターマッチングサービスへの登録:サービスを利用する保護者と直接つながるもっとも一般的な方法でしょう
- 個人ウェブサイトやSNSでの情報発信:自身の保育方針や経験をアピールし、直接依頼を受けつけます
- ベビーシッター派遣会社への登録:会社が依頼を受けるため、集客の手間が省けるのが特徴でしょう
- 地域の子育てサークルやイベントでの交流:口コミで信頼を広げることも重要です
これらの方法を組み合わせることで、より効率的に顧客を獲得し、安定した活動につなげることができるかもしれません。
保育ママ:自治体の認可事業であるため、利用者の募集や利用調整は基本的に自治体が主導します
保護者は市町村の窓口を通じて入所申込みを行い、自治体が入所先を決定するため、個人での集客活動は通常行われません。
Q4.ひとりで保育をするのは大変?
A.もちろん大変な面はありますが、その分やりがいも大きいでしょう。
ひとりで保育をすることは体力面や精神面で大変なこともあります。しかし、少人数の子どもを自宅で預かるため、一人ひとりの子どもと深く関われるという利点があるでしょう。また、保育補助者といっしょに働くことも可能です。
Q5.収入はどのくらいになる?
A.ベビーシッターと保育ママで、収入は大きく異なります。ベビーシッターの場合は、サービス内容や働き方によっても幅があるのが特徴でしょう。
ベビーシッターの場合、収入は時給や単価、そして活動時間によって大きく変動するでしょう。また、地域や夜間保育・病児保育などのサービス内容によっても幅があるのが特徴です。一般的には1時間あたり1,500円から3,000円程度が目安といわれています。収入を安定させるには、複数の利用者との定期的な契約や、長期休暇など繁忙期の依頼を増やすことがカギとなるかもしれません。
一方で、保育ママの収入は主に自治体からの委託費や助成金で成り立っています。収入額は、保育する子どもの人数や利用時間、そして各自治体の定めた報酬基準によって決まるため、一般的な保育士の給与を参考にするとよいかもしれません。詳細な金額については、各自治体の担当窓口に確認しましょう。
子どもを自宅で預かる在宅保育で理想の働き方を叶えよう
今回は、在宅保育について「ベビーシッター」「保育ママ」に分けて、仕事内容や開業するまでの流れなど、それぞれの特徴を紹介しました。
どちらも少人数の保育となり、きめ細やかでていねいな保育を行えることが特徴でしょう。その一方で、仕事を始めるにあたって、準備することや意識することに大きな違いもありました。
それらを参考に、自分がどのような環境で、どのように子どもに関わっていきたいかを考えてみるのもよいかもしれません。
こちらの記事では、保育士資格を活かして在宅ワークができる仕事を紹介しています。保育ママのほかに、保育園の事務職や保育園業務のサポートなどもあるようです。気になる方はぜひ参考にしてみてください。
自分の希望の働き方に合った個別保育サービスの開業を選択肢に入れながら、理想の保育を実現していきましょう。
「キズナシッター」なら、きめ細やかでていねいな保育を実現できます!
ベビーシッターや保育ママなど、在宅保育をしたいと考えている方のなかには、「子ども一人ひとりに寄り添ってていねいに関わりたい」という方もいるようです。
そのように感じている場合は、「キズナシッター」での活動を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターは、ベビーシッターのマッチングサービスです。給与は一般的な保育園のアルバイトよりも高く、時給は自分で設定できます。そのため、働き方によっては高収入も期待できるでしょう。勤務時間は1時間から設定でき、週1日から副業として働くことも可能です。
自分のライフワークバランスを意識しながら、理想とする保育をキズナシッターで実現しませんか。
ベビーシッターの登録はアプリから
面倒な手続きは一切不要!アプリをダウンロードしていただき、無料の登録説明会にご参加ください。