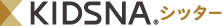産後の保育園に関する基礎知識。上の子の利用や送迎などの不安を解消する対策とは

保育園の基本情報
 Krakenimages.com / stock.adobe.com
Krakenimages.com / stock.adobe.com
これから保育園に子どもを預け、仕事を始めようと考えている方のなかには、子どもを預けられる月齢や保育時間が気になる方もいるのではないでしょうか。
まずは、保育園にいつから預けられるかや、保育時間などの基本情報について紹介します。
入園できる月齢
厚生労働省の資料によると、出産後8週間は産休期間に該当するとされています。そのため、基本的に保育園に預けられるのは生後8週目以降になるでしょう。
具体的にいつから預けられるかは、自治体や希望する保育園によって異なるため、直接問い合わせてみるとよいかもしれません。
自治体の入園相談窓口には、地域の保育園が一覧になった冊子が用意してある場合もあります。そこから、入園に関する詳細な情報を得られることもあるでしょう。また、近くに気になる保育園がある場合には、公式サイトからも預けられる月齢について知ることができるかもしれません。
出典:働きながらお母さんになるあなたへ/厚生労働省保育時間
保育園の利用時間はそれぞれの施設によって異なりますが、午前7時15分から午後6時15分までというように、11時間保育を行っている保育園が多いようです。
そのなかで、子どもを預けられる時間は、パパやママの就労時間など保育を利用する理由によって異なります。
認可保育園の場合、通勤時間や休憩時間も考慮して、保護者の就労状況などに応じて、子ども一人ひとりの保育時間が決定されます。保育時間には、「保育標準時間」認定の最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)と「保育短時間」認定の最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)の2種類があります。
そのほか、認定こども園や地域型保育などもあり、それぞれ利用できる時間も異なるようです。気になる方は、以下の資料を参考にしてください。
出典:よくわかる「子ども・子育て支援新制度」/こども家庭庁産休・育休中の上の子の保育園利用
 Makizo / stock.adobe.com
Makizo / stock.adobe.com
二人目や三人目などの出産で産休・育休を取得している方のなかには、その期間中に上の子が保育園を利用できるのか気になる方もいるかもしれません。
まず、保育園に子どもを預けるためには、「保育が必要な理由」が明確である必要があるでしょう。こども家庭庁の資料では、この保育の必要性の認定事由に、「妊娠、出産」および、「育児休業取得時に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること」という項目が挙げられています。つまり、基本的には産休中や育休中でも保育園の継続利用は可能ということになります。
ただし、保育園の継続利用については各自治体で方針が異なるため、その点については事前に確認しておく必要がありそうです。
出典:V.保育の必要性の認定・確認制度/こども家庭庁通園継続するための手続き
では、産休・育休中も上の子が通園を継続するためには、どのような手続きが必要なのでしょうか。
まずは、手続きに必要な書類の準備から始めましょう。以下は、一般的な必要書類です。
- 保育園継続のための状況申告書
- 育児休業期間証明書
- 教育・保育給付認定変更申請書兼変更届
- 給付認定証(返却)
- 税資料(提出)
- 保育の必要性の事由を証明する書類
なお、実際に必要となる書類はそれぞれの自治体によって異なるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。
必要書類が準備できたら、保育の必要性の認定申請を行いましょう。申請後に認定証の交付を受けたら、保育利用希望の申込みに進むのが一般的な流れのようです。
引き続き通園する場合の注意点
産休や育休中でも保育園を利用できる一方で、利用の際に注意すべき点もあるようです。
上の子の保育園の継続利用が認められた場合でも、登園や降園の時間が変わるケースがあるかもしれません。
産休中は通常の保育と同じく11時間預かってもらえるところも多いようですが、育休中は8時間の時短保育になる可能性もあります。なかには、お迎えの時間を指定する施設もあるようなので、基本的には保育園を利用できる時間が短くなると考えておくと安心かもしれません。
また、前述したように、上の子の保育園を継続利用するためには、自治体への申請が必ず必要になります。自治体への手続きを忘れていると、保育園が利用できなくなるかもしれないため注意しましょう。
産後に向けての保活
 japolia / stock.adobe.com
japolia / stock.adobe.com
産後、保育園に子どもを預けるためには、保育園探しが非常に大切になってくるでしょう。
ここでは、保育園入園までの流れと妊娠中の保活、保育園が決まらなかったときの対応策など、保活における重要ポイントについてまとめました。
保育園入園までの流れ
子どもを保育園に入れたいと思ったときには、まず「保育園探し」から始めます。居住エリアや職場の近くにどのような保育園があるか調べてみましょう。
入園時の子どもの月齢や年齢、保育園までの距離、保育内容など希望にあった施設を探していくことが大切になってくるでしょう。気になる保育園が見つかったときには、保育園の詳細な情報を調べたり、実際に見学に行ったりすることも必要になってくるかもしれません。
希望するクラスに空きがある場合には、すぐに入園手続きを行える可能性もありますが、空きがなく年度途中の入園が厳しい場合もあるようです。その場合は、年度初めの4月入園の申込みとなるため、自治体のスケジュールにあわせて入園書類を準備し、提出する必要があるでしょう。
入園が決まると、自治体、もしくは内定した保育園から連絡があり、入園に向けて健康診断や入園説明会が行われる場合もあるようです。
なお、このような入園申込みの流れは、自治体によって大きく異なるため、早めに詳細を確認することが重要になってくるでしょう。
以下の記事では、基本的な保活の流れや保活を有利に進める方法などを紹介しています。あわせて参考にしてみてください。
妊娠中の準備
出産後、子育てが落ち着いたタイミングで保育園の入園を考えている場合は、妊娠中の保活も大切になってくるようです。
産後は、ママの体調を回復させる時期であるのに加え、赤ちゃんのお世話で思うように動けなかったりすることもあるかもしれません。そのため、妊娠中の体調がよいときに、希望にあった保育園の見学に行ったり、入園に必要な書類を用意しておいたりすると、申込みをスムーズに行うことができるでしょう。
妊娠中は、ママの体調を最優先に考え、パートナーと協力しながら計画的に保活を進められるとよいかもしれません。
以下の記事では、妊娠中の保活について紹介しています。不安や疑問を解決し、しっかりと準備していきましょう。
上の子と同じ施設への入園
下の子が上の子と同じ施設へ入園すると、送迎の手間が省けたり、きょうだいが同じ環境で成長できたりするなど、さまざまなメリットがあるでしょう。しかし、状況によっては確実に希望が叶うわけではないようです。
多くの自治体では、入園選考の際に「きょうだい加点」が設けられているようですが、この点数や条件は、自治体によって大きく異なります。また、加点があっても確実に入れるわけではないことも考慮しておきましょう。
ママのなかからは、希望する園の年齢ごとの定員や、例年の入所状況をこまめにチェックすることが重要だという声もありました。入園に関する自治体の相談窓口なども活用して、きょうだい加点の詳細や、過去の入園状況について情報収集することが入園のカギになるかもしれません。
育休中の保育園申込みについての詳細は以下の記事から確認できます。入園のタイミングや申込み時期、必要な手続きなども紹介しています。
入園できなかったときの対応策の検討
希望する保育園に内定が決まらない場合のために、対応策について考えておくことも大切でしょう。そうすることで、落ちたあともすぐに次の行動に移せるかもしれません。
たとえば、認可外保育園は、認可保育園のように細かな選考基準がなく、申込み順に内定が決まることが多いようです。認可保育園に落ちたあとでも申込みを行うことができるため、保育園探しの際には、認可外保育園についても調べたり、見学に行ったりしておくと安心でしょう。
また、ママのなかからは、預け先が決まるまでの間、民間のベビーシッターを利用したという声も聞かれました。
自治体によっては、一定期間の認可外施設やベビーシッターの利用は、認可保育園の入園申込み時に加点対象となることもあります。年度途中や次年度の入園が有利になるため、自治体の入園案内をしっかり確認しておきましょう。
以下の記事では、希望園に入園できないときの具体的な対処法を紹介しています。家庭の状況にあった工夫をしながら前向きに保活を進めましょう。
【体験談】上の子の送迎に関する悩み
 kapinon / stock.adobe.com
kapinon / stock.adobe.com
上の子が保育園に通園している家庭の悩みのひとつに、産後の上の子の送迎があるようです。
ママやパパたちがどのような点で悩んでいるのか体験談を紹介するとともに、それらへの対処法を考えます。
送迎方法
産後の上の子の送迎については、家庭の状況によってさまざまな悩みが出てくるかもしれません。ママやパパは、自宅からの距離や天候によって送迎手段も変わってくるため、常に状況をみながら適切な判断ができるように努めているようです。
ベビーカーに上の子が乗れるステッパーを装着して負担を軽減したり、おんぶできるタイプの抱っこ紐を使用したりと、さまざまな工夫が聞かれました。
サポートを依頼する相手
朝の送りをパパが、帰りのお迎えをママが担当するなど、うまく分担しているという声や、近くに両親や義父母が住んでいる家庭は、ママの体調が安定するまで送迎の協力してもらったという声などがありました。家族だけで対応できないときに、ベビーシッターサービスを活用しているという家庭もあるようです。
育児サービスの活用
ファミリー・サポート・センターとは、自治体が主体となって運営している事業で、保育園までの送迎やお迎え後の預かり保育など、依頼できる内容もさまざまのようです。このサービスを利用するためには、自治体に事前登録が必要になってくるようです。
また、ベビーシッターサービスは、保護者が不在のときに利用できるだけではなく、保育園の送迎の代行サービスを行っている場合もあります。お迎え後に自宅でのシッティング依頼をすることもできるため、子どもの遊び相手になってもらったり、赤ちゃんのお世話をサポートしてもらったりすることも可能でしょう。利用を検討するときには、サービス内容や料金を確認し、希望にあったベビーシッター会社に事前登録しておくとよいかもしれません。
以下の記事では、ベビーシッターへの送迎依頼に関するママ・パパたちの体験談や料金の目安などを紹介しています。気になる方はチェックしてみてください。
産後の保育園利用に関するよくある質問
 folyphoto / stock.adobe.com
folyphoto / stock.adobe.com
産後の保育園利用について、さまざまな悩みを抱えているママやパパも少なくないでしょう。ここでは、それらの疑問と答えを紹介します。
Q1.産休・育休中に、上の子は同じ保育園に継続して通い続けられる?
A.多くの自治体で、産休・育休中でも上の子は保育園に継続して通園できるようです。しかし、利用可能な期間や条件は自治体や園によって異なります。自治体の入所案内を確認するか、直接問い合わせてみましょう。また、育休期間中の保育時間が短縮される「短時間保育」の利用を求められる場合もあるかもしれません。
Q2.下の子が生まれたら、保育園の送迎はどうすればいい?
A.産後すぐは体調が万全でないことも多いため、無理のない送迎方法を検討することが大切でしょう。パートナーや家族に依頼したり、地域のサポート事業やベビーシッターによる送迎サービスを利用したりすることも選択肢のひとつかもしれません。
Q3.下の子の保活はいつから始めるべき?
A.産後の保活は、出産前から始めることが理想でしょう。妊娠中から、自治体の入所案内や入園選考の点数表を確認し、希望する園の見学や情報収集を始めましょう。上の子が在園している場合、きょうだい加点があるかどうかや、その点数や条件を早めに確認しておくことが重要です。多くの自治体では、下の子の入園申請は出生後に行うようですが、入園希望月の数カ月前が申請期間になることが多いため、事前にスケジュールを把握しておきましょう。
Q4.産後、上の子の保育園での生活に変化はある?
A.産後は、上の子の生活に変化が起こる場合もあるでしょう。具体的には、下の子の授乳や夜泣きなどで、生活リズムが変わり、上の子も影響を受けることが考えられます。弟や妹が生まれることで、上の子の気持ちが不安定になったり、赤ちゃん返りが起こったりすることもあるでしょう。産後の上の子の様子について、園の先生と密に情報共有したり連携を取ったりして、家でも上の子と向き合う時間を意識的に作るとよいかもしれません。
Q5.きょうだいが別の園に通うことになってしまった場合、どうすればいい?
A.きょうだいが別の園になってしまった場合、送迎が最大の課題となるでしょう。きょうだいそれぞれの送迎時間をずらして対応したり、自宅からふたつの園への送迎ルートを事前に確認したりして、効率的な工夫を考えましょう。なかには、上の子か下の子どちらかの送迎を、ファミリー・サポート・センターやベビーシッターサービスに依頼する家庭もあるようです。
出産後の保育園は早めの準備がカギ
今回は、保育園の基本情報や保活内容、産後の二人目の保育園の送迎などについて紹介しました。
保活は、自治体の情報を把握することが非常に重要になってきます。早めの情報収集を心がけ、計画的に進めていけると安心かもしれません。また、現在保育園に子どもが通っている場合には、上の子の送迎についても、どのように対応していくのか早めに家族と相談しておくことが大切でしょう。
ベビーシッターサービスを利用したり周りの協力を得たりしながら、産後も親子それぞれ気持ちよく保育園に通えるとよいですね。
保育園の送迎も「キズナシッター」なら安心
子どもの預け先や保育園の送迎の対応に悩んだ場合には、子どもを安心して預けられるベビーシッターサービス「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士、幼稚園教諭、看護師などの国家資格を全員が保有しています。そのため、子どもに関する専門知識をしっかり持った経験豊富なベビーシッターが多いことが魅力のひとつでしょう。
担当するベビーシッターは、利用者自身がプロフィールやレビューを参考に選ぶことができます。特定のベビーシッターの定期利用も可能なため、信頼関係が築きやすいことも特徴です。料金設定についても、入会金や年会費は一切かからず、利用した分だけの支払いになるため、初心者にも利用しやすい内容といえるでしょう。
キズナシッターへの登録は無料です。いざというときのために、この機会にぜひ、会員登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。