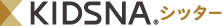幼稚園の延長保育は使いやすい?利用方法・料金、働くママの体験談

子どもが幼稚園に通っている家庭の悩み
子どもの入園に際して、幼稚園のお迎え時間や、何時まで子どもを預けられるのかは、ママやパパにとって気になるポイントかもしれません。実際に、子どもが幼稚園に通うママたちは、お迎えの時間と仕事の両立に悩んでいるようです。
このように幼稚園の保育時間が短いことで、さまざまな悩みの声が聞かれました。
しかし近年、幼稚園でも共働き家庭が増加している背景から、保護者の要望にあわせて長時間子どもを預かる「延長保育」を実施する幼稚園も増えてきています。厚生労働省の資料によると、令和元年度では公立・私立あわせて87.8%の園で延長保育(預かり保育)を実施していることがわかります。
就労などを理由に子どもを長く預けたい場合には、まずは延長保育を利用できる幼稚園を選ぶことが重要になってくるかもしれません。
出典:幼稚園における預かり保育の推進/厚生労働省幼稚園の延長保育とはどんな制度?

延長保育とは、幼稚園の基本的な預かり時間を超えて預かってもらうことです。園によっては、延長保育のことを「預かり保育」と呼ぶこともあり、呼び方はさまざまのようです。
なかには、延長保育が未実施の幼稚園もあるものの、前述したように、「集団生活の中で教育を受けさせたい」「仕事が終わる時間まで預かってほしい」という保護者のニーズから、多くの幼稚園では延長保育を実施しています。
一般的に、幼稚園の標準保育時間は4時間程度と短いため、長く預かってもらえる延長保育は、働くママやパパにとっては助かる制度かもしれません。
幼稚園の延長保育を利用する理由
幼稚園の延長保育を利用する際、どのような理由で子どもを預けることができるのか気になる方もいるでしょう。ここまでお伝えしてきたように、仕事を理由に延長保育を利用する家庭は多いようですが、それ以外の理由で延長保育が利用できる園もあるようです。
ママたちの声を一部ピックアップして、紹介します。
仕事
このような共働き家庭にとって、延長保育はなくてはならない存在となっているようです。延長保育で子どもも楽しくすごすことができれば、親も気持ちよく働けるかもしれません。
用事
子どもをいっしょに連れていくことができない用事がある場合、延長保育はママやパパにとって心強い味方になりそうです。ほかにも、病院での長い待ち時間を懸念して、通院時は必ず延長保育を利用しているというママの声も聞かれました。
リフレッシュ
園によってはリフレッシュ目的で延長保育を利用できることもあるようです。なお、延長保育が利用できる条件は園によって異なり、理由に関係なく誰でも利用できる場合や、保護者の就労や用事があり、子どもを見られない環境のときのみ利用できる場合など、さまざまなようです。
また、延長保育の利用は、事前申込みが必要な場合もあるため、急な用事ができたときなどにも対応してもらえるのか、事前に確認をしておくと安心かもしれません。
幼稚園の延長保育の時間帯と内容

幼稚園は子どもが通う教育機関で、国が定める「学校教育法」では学校の一種とされています。
では、そのような幼稚園で行われる延長保育とは具体的にどのようなものなのでしょうか。ここでは、延長保育の時間帯と内容についてお伝えします。
何時まで?
幼稚園の延長保育を利用したとしても、預かり終了時間が早いと、お迎えの時間に間に合わないこともあるかもしれません。
一般的に、標準保育時間の前後が延長保育(預かり保育)の時間となり、保育時間後ではおおむね14時~17時頃まで預かる園が多いようです。なかには、18時以降も預かってもらえるところもあり、保育園並みに遅くまで受け入れてくれて助かるというママやパパの声も聞かれました。
また、幼稚園には保育園と違い、夏休みや冬休みといった長期休みがあります。そんな長期休みにも、通常保育が始まる前の朝7時半や8時などから子どもを預けられる幼稚園も多くあるようです。仕事をしている、もしくはしたいと考える方は、長期休みでも預かり保育を利用できる幼稚園を選ぶとよいかもしれません。
なお、延長保育の実施時間は、それぞれの幼稚園によって「登園前の預かりはなし(通常保育後の預かりのみ)」「平日の預かりのみ(長期休みはなし)」などとルールが決められているため、利用を検討する際は事前に確認しておきましょう。
どんなことをしてくれる?
延長保育では、創作遊びや工作、絵本、お外遊びなどの自由遊びがメインとなるようです。
異年齢で遊ぶ機会があったり、放課後は遅くまですごすことからおやつが提供されることもあったりと、子どもにとっても楽しい環境が整っているというママの声もありました。
なかには、延長保育中に英語や体操など、習い事のような課外活動を取り入れている幼稚園もあるようです。共働きで習い事に通わせるのが大変な家庭にもありがたい内容といえるでしょう。
幼稚園の延長保育の利用料金
延長保育の料金は、それぞれの幼稚園で設定しているため、地域や園によっても異なります。
たとえば、1回いくらと決め、利用した分を支払う場合や、月額いくらと設定している場合など、さまざまなようです。また、園によっては、一定の時間まで無料で延長保育を行っているところもあるため、違いが大きい部分といえるかもしれません。
実費となる例
基本的に、幼稚園の延長保育料に関しては実費となります。この延長保育料のほか、おやつ代が発生する場合や、土曜日や長期休みに利用するときには料金設定が通常と異なることもあるようです。
ただし、2019年10月に始まった幼児教育無償化により、条件を満たせば幼稚園の延長保育も無償化の対象となります。この条件とはどのようなものなのでしょうか。
無償化の条件
幼稚園の預かり保育で無償化の対象となるには、新2号認定を取得する必要があります。この新2号認定とは、自治体から受ける「保育の必要性の認定」のことをいいます。
しかし、無償化の条件である新2号認定は、就労しているというだけでは受けられません。たとえば、月48時間以上働いているなど、一定の時間働いていることが必要となります。
また、預かり保育の利用料は全額が無償化の対象となるわけではなく、「預かり保育を利用した日数×450円」と「預かり保育の利用料」のどちらか小さい方が無償となります。(上限月11,300円)
なお、新2号認定を受けるために必要な就労時間は各自治体によって異なるので、必ず居住地域の条件を確認しておきましょう。
出典:幼児教育・保育の無償化概要/こども家庭庁仕事以外で無償化適用されるケース
幼稚園の延長保育は、仕事以外にも出産や求職中でも認められます。以下に、一部抜粋しました。
- 出産
- 疾病・障害(保護者本人)
- 3親等以内の親族の介護・看護
- 災害復旧
- 求職
- 就学 など
このように、保育の必要性の認定基準は上記の場合にも当てはまるため、延長保育においても無償化が適用されます。延長保育枠の空き状況によっては、年度途中からでも預けられるケースもあるようなので、保育が必要な状況になったら申請してみてもよいでしょう。
出典:Ⅴ.保育の必要性の認定・確認制度/こども家庭庁子どもの預け先に悩んだときの対処法

ここまで幼稚園の延長保育についてお伝えしてきましたが、子どもが通う幼稚園の条件に当てはまらなかったり、利用したいときに空きがなかったりする場合もあるかもしれません。
そんなときはどのように対処すればよいのでしょうか。ママたちに聞いてみました。
家族やママ友と協力する
近くに両親が住んでいる場合は、いざというときも依頼しやすいようです。ほかにも、親しいママ友に、お友だちといっしょに子どもをみてもらうようお願いしたという声も聞かれました。いずれにしても、用事が済んだら早めにお迎えに行くよう心がけ、相手への配慮を忘れないことが大切かもしれません。
ファミリーサポートを利用する
子どもの預け先として、ファミリー・サポート・センターを利用したママがいました。ファミリー・サポート・センターを利用するためには、事前に会員登録をする必要があるようなので、気になる方は自治体の登録内容などを確認してみましょう。
ベビーシッターに依頼する
ベビーシッターサービスを利用して、子どもと留守番してもらった家庭があるようです。ママのなかからは、初めてベビーシッターサービスを利用するときは、インターネットや友だちからの口コミを重視して選んだという声も聞かれました。ベビーシッターサービスを利用する際は、サービス内容やベビーシッターの資格の有無などを確認し、事前に面談を行ったうえで依頼すると安心かもしれません。
幼稚園の延長保育は家庭のライフスタイルにあわせて
幼稚園の延長保育の仕組みは、それぞれの園によって大きく異なります。就労などを理由に、延長保育を考えているときは、料金や理由、何時まで見てもらえるのかなどの条件をポイントに、家庭のニーズにあわせて利用できるとよいかもしれません。
また、幼稚園の延長保育を利用できない場合の選択肢も視野に入れておくと、ライフスタイルの変化にもスムーズに対応できるでしょう。親子ともども気持ちよくすごせるように、子どもの預け先もうまく工夫できるとよいですね。
子どものお迎えに遅れそうなときは「キズナシッター」の活用を
子どものお迎え時間に不安を抱えたときには、「キズナシッター」の利用を検討してみてはいかがでしょうか。キズナシッターでは、学童や保育園の送迎サービスも実施しています。
また、子どものお迎え後、保護者が帰ってくるまでの間、自宅でのシッティングもお願いできるため、残業や会議で帰りが遅くなるときにも安心して利用することができます。
キズナシッターでは、登録スタッフの全員が保育士や幼稚園教諭、または看護師の国家資格を所有しています。そのため、保護者からは「子育てのプロとしてそれぞれの子どもの様子に応じた、ていねいなシッティングをしてくれる」と好評です。
専用のアプリから会員登録することで、ベビーシッターの選択や依頼、支払いまでを一括で行えるため、子育てや家事で忙しいママやパパも利用しやすいといえるでしょう。子育てのパートナーのひとりとして、この機会にぜひキズナシッターの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。