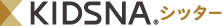乳幼児期はいつまで?乳児・幼児それぞれの期間と特徴、意識したい育児ポイント

乳幼児期はいつからいつまで?
赤ちゃんが生まれたあと、「乳幼児」という言葉をよく耳にするようになったという方も少なくないのではないでしょうか。なかには、その乳幼児期がいつからいつまでを指すのかや、乳児と幼児の切り替わりはいつなのかを知りたい方もいるかもしれません。
今回の記事では、法律で定められている乳幼児の期間と、ママ・パパたちが「乳児から幼児になった」と感じたタイミングなどをお伝えしていきます。
乳児は何歳まで?
 ucchie79 / stock.adobe.com
ucchie79 / stock.adobe.com
まずは、「乳児」とは何歳までを指す言葉なのか、厚生労働省や文部科学省の資料をもとに紹介します。
期間
児童福祉法や母子健康法によると、「乳児」は1歳未満である者と定義されています。つまり、誕生から1歳の誕生日を迎えるまでの赤ちゃんは(0歳の間)は「乳児」と呼ぶということです。
出典:②提出各種法令による児童等の年齢区分/厚生労働省特徴
乳児期の赤ちゃんは、さまざまな環境の変化に対応しながら著しく心身が発達する時期であるとされています。特に視覚や聴覚、嗅覚などが敏感で、泣いたり笑ったりといった表情の変化なども見られます。さらに、身体の動きや喃語によって、自分の欲求を表現することもこの時期の特徴のようです。
出典:3.子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題/文部科学省幼児は何歳まで?
 miya227 / stock.adobe.com
miya227 / stock.adobe.com
次に、「幼児」といわれる期間や特徴を、厚生労働省や文部科学省の資料をもとに紹介します。
期間
児童福祉法や母子健康法では、満1歳から小学校就学前の期間が「幼児」と分類されています。1歳の誕生日から小学校入学までと考えるのが一般的でしょう。
出典:②提出各種法令による児童等の年齢区分/厚生労働省特徴
文部科学省の資料では、幼児期は、身近な人や周囲のもの・環境と関わり始める時期であり、徐々に興味や関心の対象を広げていくとされています。よって、認識力や社会性を育むとともに、食事や排泄、睡眠など基本的な生活習慣を身に着けていく時期といえそうです。
また、子ども同士で遊ぶことなどで想像力が豊かになり、さまざまな体験を通じて道徳性や社会性の基盤が育まれていく時期でもあるようです。
出典:3.子どもの発達段階ごとの特徴と重視すべき課題/文部科学省乳幼児期の育児ポイント
一般的に発達が著しく、どんどんできることが増えていくといわれる乳幼児期。一日のほとんどをママやパパとすごすため、親からの愛情を多く感じる時期でもあるようです。
そのような乳幼児期ならではの特徴に応じて、どのような育児をすればよいか気になる方も少なくないのではないでしょうか。ママやパパたちに聞いてみると、主に以下の3点を意識している方が多いようです。
- たくさん話しかける
- スキンシップを大切にする
- 年齢に合わせた対応をする
乳幼児期は、ママやパパとコミュニケーションを取ることが心や身体の発達に重要だとされています。特に、人間関係においては、乳幼児期の愛着を基盤にして他者との関係性を築いていくともいわれているようです。
子どもの将来のためにも、以上のポイントを意識しながら親子の絆を深めておくとよいかもしれません。
乳児から幼児になったと感じたエピソード
 taka / stock.adobe.com
taka / stock.adobe.com
成長が目覚ましい乳幼児期のなかで、ママやパパたちは、どのようなシーンで乳児から幼児になったと感じているのでしょう。そのように感じたタイミングやエピソードを聞いてみました。
乳児用のグッズを卒業したとき
ベビーカーに乗らず、歩いてお出かけをするようになったときに、乳児から幼児になったと感じたママがいました。ほかには、抱っこ紐を使わなくなったときや、ストローマグからコップに切り替わったときなどといったママやパパの声もありました。
ママやパパから離れて行動するとき
ママから離れてひとり遊びをする行動に、子どもの成長を感じたママもいました。パパのなかには、同年代の子どもの輪に入って遊び始めたときに乳児期の終わりを感じた方もいるようです。
意思の疎通や会話が増えたとき
意思の疎通がとれたことで乳児期の終わりが見えたというママもいました。簡単な言葉でのやりとりができるようになったときに、乳児から幼児になりつつあるんだなと感じたというパパの声も聞かれました。
子どもの月齢や年齢による呼び方の使い分け
ここまで、「乳児」「幼児」という呼び方についてお伝えしてきましたが、ほかにも子どもの呼び方にはさまざまなものがあります。ここでは、「乳児」「幼児」以外の子どもの呼び方とその使い分けについて紹介します。
赤ちゃんとは
小さな子どもを指す名称として代表的なのが「赤ちゃん」です。パッと見たときに月齢や年齢が分からなくても呼びやすいのが特徴でしょう。
赤ちゃんの呼び名は、産まれたばかりの子どもの皮膚が赤く見えることが由来とされています。赤ちゃんのほかに、「赤子」「赤ん坊」などと呼ばれることもあるでしょう。
このように赤ちゃんは、本来であれば「産まれて間もない子」を指しますが、人によっては歩き始めの頃の子どもを赤ちゃんと呼ぶこともあるようです。乳児や幼児は、対象となる時期が限定されますが、赤ちゃんは「小さな子ども全般」のことを呼んでいるといえるでしょう。
新生児とは
出産後、産院などでよく使われる呼び名が「新生児」です。新生児とは、産まれてから生後28日未満の赤ちゃんのことを指します。
生後何日かをカウントするとき、産まれた日を生後0日とするか、もしくは1日目とするか悩む方もいるかもしれませんが、新生児期の数え方は、産まれた日を0日目として計算するのが一般的のようです。よって、28日目は含みません。
つまり、産まれてから生後28日未満の場合、「赤ちゃん」「乳児」「新生児」と、さまざまな呼び方ができるということになります。
出典:母子保健法/厚生労働省小児とは
子どもが成長していくなかで、「小児」という呼び方に出会う機会も多くなるでしょう。
児童福祉法では、小児は「出生から春機発動期(思春期)まで」とされています。女児は14・15歳、男児は16・17歳までと定められていますが、思春期という言葉はあいまいで個人差があるかもしれません。
また、小児と同じ年齢の子どもを指す言葉に「児童」「学童」などもあります。どちらも小学生に対する名称ですが、以下の厚生労働省の資料からもわかるように、小児は主に医療や看護の用語として使われることが多いようです。
さらに、旅客及び荷物運送規則では、小児は「6歳から12歳未満」と記載されています。飛行機や電車の運賃などで使われることも多いため、正しく理解しておくと便利かもしれません。
出典:医療法施行規則第十六条に関する疑義について/厚生労働省乳幼児期の特徴を理解して育児を楽しもう
 taka / stock.adobe.com
taka / stock.adobe.com
乳幼児期がいつまでなのかは、生後0日から1歳の誕生日を迎える前日までが乳児、1歳から小学校就学前日までが幼児と児童福祉法や母子健康法で定められています。
乳児から幼児へ成長したと感じるシーンは、ママやパパによってそれぞれのようですが、具体的には乳児用グッズを卒業したときや意思疎通ができるようになったときなどが挙げられるようです。
成長著しいこの時期は、過ぎたあとに振り返ると短かったと感じる方もいるようです。今回紹介した育児ポイントも参考にしながら、乳幼児期ならではの育児を楽しめるとよいですね。
乳幼児期の赤ちゃんや子どものサポートは「キズナシッター」
乳幼児と暮らすママやパパのなかには、「子連れで行きにくい用事があるので、誰かに預かってほしい」「たまには自分の時間もつくりたい」と悩む方もいるようです。
そのように育児のサポートが必要なときは「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターは、0歳から12歳までの赤ちゃんや子どもを対象とした、ベビーシッターのマッチングサービスです。シッティングを担当する方は、全員が保育士や幼稚園教諭、看護師いずれかの国家資格を所有しています。
国家資格所有率100%のキズナシッターは、初めてベビーシッターサービスを利用する家庭からも専門性が高いと好評です。会員登録や年会費は一切かからないため、いざというときのために、まずはキズナシッターの登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。