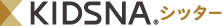腹ばいとは?うつ伏せ・ずりばいとの違いや成長過程で大切だといわれる理由

腹ばいとは
赤ちゃんにとっての腹ばいとは、お腹を下にして寝そべったときに首を持ち上げる動きのことを指すといわれています。腹ばいは、首座りや寝返り、お座りなどのさまざまな動きにつながる動作とも考えられているそうです。
うつ伏せとずりばいとの違い
腹ばいと同じような動きに、うつ伏せやずりばいといった言葉があります。ママやパパのなかには、それらが腹ばいとどう違うのか気になる方もいるでしょう。
うつ伏せは、頭を下げて体全体を下向きに床につけている状態を指します。腹ばいと非常に似た姿勢といえますが、これらには、「頭を上げているかどうか」と「意識はあるかどうか」という相違点があるようです。
つまり、うつ伏せは睡眠姿勢、腹ばいは起きている時にとる姿勢というように考えるとイメージがつきやすいかもしれません。
また、ずりばいは、お腹を床につけたまま腕や足の力で前や後ろに移動することを指すといわれています。
腹ばいで移動するほふく前進のような動作というと分かりやすいのではないでしょうか。
腹ばいが赤ちゃんにとって大切な理由
赤ちゃんの定期健診で、腹ばいができるかどうかかかりつけ医の先生に聞かれたことがあるという保護者の方も多いかもしれません。
腹ばいは、赤ちゃんの筋力や運動能力の発達を促すといわれているようです。
また、首が座る前の赤ちゃんが頭を持ち上げたり横に向けたりしようとするのは、首から背中、肩甲骨周辺の筋肉の発達や、身体を支えるためのバランス感覚によい影響があるそうです。
さらに、腹ばいをすることで視点が変わり、よい刺激になったり呼吸機能にもよい影響があったりするといわれています。
腹ばいを始める時期

赤ちゃんの成長過程のなかで、重要な役割を果たしている腹ばい。ママやパパのなかには、「そろそろ腹ばいを始める時期かもしれない」とそわそわしている方もいるかもしれません。
ここでは、腹ばいを始める時期とそのなかで腹ばいの練習を取り入れていたかどうかについての体験談を紹介します。
腹ばいで遊ばせるのは生後2カ月頃から
ママの体験談にもあるように、一般的には生後2カ月頃から腹ばいの姿勢ができるようになってくるようです。
なかには、3カ月頃になるとひじで支えることができるようになり、余裕をもってママとパパと遊ぶようになったという声もありました。
それまではずっと仰向けでいた赤ちゃんも、腹ばいになることで景色ががらりと変わり、今まで気がつかなかったものをたくさん見つけることができるようになるかもしれません。
腹ばいの練習は赤ちゃんの様子を見ながら
赤ちゃんの身体の動きをサポートするきっかけとして練習を取り入れたというママがいる一方で、練習しなくてもいつの間にか腹ばいができるようになっていたというママもいました。
練習をする場合は、仰向けに寝たママのお腹の上に赤ちゃんを乗せて、腹ばいの状態ですごす時間を作ってみてもよいかもしれません。
そのようななかで、腹ばいの姿勢を嫌がって激しく泣いたというパパの声も聞かれました。
練習をするしないにかかわらず、赤ちゃんの様子をみながら無理をさせることがないよう気をつけることが大切かもしれません。
腹ばいの練習方法

腹ばいの練習をするかどうかは家庭によってさまざまなようですが、練習をする場合は具体的にどのようにしたらよいのでしょうか。
ママとパパに聞いた腹ばいの練習方法を、順を追って紹介していきます。
まずは場所の確保をする
練習がしやすいように、最初に腹ばいができるような環境を確保したというママがいました。
ほかにも、固めのマットレスの上にバスタオルを広げて練習したという家庭もありました。
赤ちゃんを腹ばいにさせる
赤ちゃんを腹ばいの姿勢にしたあと、苦しそうにしていないか様子を確認することも大切でしょう。
パパのなかからは、腹ばいの姿勢にするときは、足の方からゆっくり降ろし、最後に顔がつくようにしていたとの声も聞かれました。
正面から声をかける
赤ちゃんと同じ目線になって声をかけてあげるのもよさそうです。
赤ちゃんの興味を引くために、ガラガラや鈴など、音の出るおもちゃを活用して、首を上げられるように工夫したパパもいました。
腹ばいの練習をするときに意識したこと

ママやパパはさまざまなことに配慮しながら工夫して腹ばいの練習を行なっているようです。
では、そのような練習をする際、具体的にどのようなことに気をつけたらよいのでしょうか。聞いてみました。
授乳後は時間をあける
授乳後の練習は避け、時間をあけてから取り入れるとよさそうです。
ほかには、授乳と睡眠を繰り返すような時期だったので、起床後の機嫌のよいときに腹ばいを取り入れ、少し身体を動かしてから授乳するというリズムにしていた家庭もありました。
短い時間から始める
練習の時間を意識しながら、少しずつ伸ばしていくと赤ちゃんも無理なく取り組めそうです。
一度に長くやろうとせず、毎日できるときに少しずつ取り入れていたというママの声も聞かれました。
赤ちゃんの様子に合わせる
腹ばいの練習は、赤ちゃんの体調や機嫌に合わせて行なうことが大切でしょう。
腹ばいの体勢を嫌がる赤ちゃんもいるようなので、スキンシップ遊びのなかで腹ばいを取り入れるなどの工夫をしてみてもよいかもしれません。
腹ばいとはいろいろな動きにつながる第一歩

腹ばいとは、うつ伏せの状態から首を持ち上げる動きのことを指すようです。この腹ばいは赤ちゃんのさまざまな発達を促すともいわれています。
腹ばいの練習をする場合は、安全に行なえる場所を確保し、実際に腹ばいの姿勢にして正面から声をかけるとよいようです。その際に気をつけることとして、授乳直後は避けること、短い時間から始めることという体験談が聞かれました。
腹ばいはいろいろな動きにつながる第一歩ともいわれているため、赤ちゃんの様子をみながら機嫌のよいときに取り入れていけるとよいですね。
新生児期から子育てのサポートは「キズナシッター」へ
新生児期のママやパパのなかには、「まとまった睡眠時間がほしい」「自宅での子育てをサポートしてもらいたい」といったケースもあるようです。新生児からの子育てをサポートしてもらいたいときは「キズナシッター」を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師といった専門の知識や資格をもった方のみが登録しているベビーシッターサービスです。新生児期から対応していており、ご自宅に訪問し、授乳や沐浴、寝かしつけなどの子育てもサポートします。
キズナシッターのサービス提供時間は24時間となり、夜間保育も受け付けています。また、前日の予約にも対応可能なため、急に依頼したいと思ったときにも利用しやすいでしょう。近くに頼れる家族がいない、きょうだいの育児もあり休む暇もないといった場合には、キズナシッターの力を借りて、ゆっくりする時間を作ってみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。