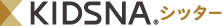18時まで仕事のワーママはどんな生活をしている?子育てと両立するための工夫

ワーママはどのくらいいる?
女性の社会進出が進み、子育てと両立しながら働く女性が増え続けています。
厚生労働省の資料によると、18歳未満の子どもと母親がいる世帯は推計で927万4000世帯で、このうち母親が働いている世帯は721万2000世帯となり、77.8%を占めました。この割合は、これまでの調査でもっとも高い結果となっているようです。
こういった背景には、短時間勤務や男性の育休取得などの環境が整備されたことが挙げられるのかもしれません。一方で、働く女性が仕事と子育ての両立を難しいと感じていることも実情のようです。
出典:結果の概要(P.8)/厚生労働省ワーママの1日の勤務時間
 wheeljack / stock.adobe.com
wheeljack / stock.adobe.com
仕事と子育ての両立に悩むワーママたちの1日の勤務時間はどのくらいなのでしょうか。ママたちに働く時間について聞いてみました。
8時間
正社員や契約社員として8時間勤務をしているママたちがいました。フレックスタイム制を導入している会社に勤めているママからは、朝の時間にゆとりが持てるように、出勤時間を遅めにしているという声も聞かれました。
6時間以上
子どもが成長するまで、短時間勤務申請をして働くママもいるようです。朝夕に時間のゆとりがあると、家事や育児もしやすいかもしれません。
5時間以下
1日5時間以下という勤務形態のママがいました。なかには、子どもが小学校に入学して帰宅時間が早くなったため、9時から15時の5時間勤務に変更したところ、仕事と家庭の両立がしやすくなったというママの声もありました。
18時までの勤務時間を調整したいと感じるシーン
 miya227 / stock.adobe.com
miya227 / stock.adobe.com
ワーママたちはそれぞれのライフスタイルによって、さまざまな勤務形態で働いているようですが、子どもが保育園に在園している家庭のなかには、「18時」が働く時間のボーダーラインになっている方もいるのではないでしょうか。これは、18時を過ぎると延長保育枠と定めている園も多いからです。
そこで、18時まで仕事をしているワーママたちに、どのようなシーンで勤務時間を調整したいと考えるのか、聞いてみました。
自分の体調がすぐれないとき
自分の体調を考えて勤務時間を少なくしたママがいました。ほかにも、仕事で疲れてイライラしている母親よりも、ゆとりをもって笑顔で接することができる母親の方が、子どもにとっても幸せだと思うという声もありました。
ライフスタイルの変化に合わせて勤務時間を調整できると、ワーママとして生活しやすいかもしれません。
家族との時間を大切にしたいとき
家族のために勤務時間を調整することも少なくないようです。なかには、子どもの幼稚園の行事に参加しやすくするために、しばらくパートタイマーとして働くことにしたというママの声もありました。
時間調整できないときの対処法
自分や家族のために働く時間を調整している方がいる一方で、勤務時間をなかなか調整できないという方もいるでしょう。では、そのようなとき、ワーママたちはどのように対処しているのでしょうか。
ここでは、どうしても自分で対応できないときに頼った相手を、ママたちの声からいくつかピックアップして紹介します。
両親
自宅近くに両親の家があると、仕事で遅くなるときなどに保育園の送迎や預かりを依頼しやすいかもしれません。自分が仕事を休めない日に子どもが体調不良になったときは、丸一日預かってもらうこともあるというママの声もありました。
ファミリー・サポート・センター
地域で行われているファミリー・サポート・センター事業を利用しているママもいるようです。会員登録をすると、ファミリー・サポート・センターが窓口になって利用調整してくれるため、働くママにとって心強い存在になってくれるかもしれません。
ベビーシッターサービス
ワーママとして働くとき、ベビーシッターサービスを活用すると、急な残業や時間外勤務の際に便利かもしれません。なかには、休日出勤や出張で一日留守にするときにも預けやすいという声もありました。
ワーママとして働くときは勤務時間や子どもの預け先を工夫しよう
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
ワーママの勤務時間は、8時間や6時間、5時間以下など働き方や家庭によってさまざまなようです。なかには18時までの仕事に疲れ、自分や家族のために勤務時間を調整しているママもいました。
仕事や家庭の都合で時間調整が難しい場合は、ベビーシッターサービスなどの預け先を活用できると仕事と子育ての両立が無理なく叶うかもしれません。それぞれのライフスタイルに応じて、まわりの協力も得ながら、仕事も子育ても楽しめるとよいですね。
勤務時間を調整できないときには「キズナシッター」の活用も
ワーママとして働いている方のなかには「勤務時間を調整できないときに子どもを預かって欲しい」「休日出勤をするときに1日子どもを預けたい」と考える方もいるのではないでしょうか。
そんなときは、子どもの預け先として「キズナシッター」の利用を検討してみてはいかがでしょう。
キズナシッターは、ベビーシッターとして登録する全員が保育士や幼稚園教諭、看護師などの国家資格を所有しています。0歳の赤ちゃんから12歳の子どもまでのシッティングが可能なため、働くママたちから、子どもが成長してからも預けやすいと好評を得ています。
専用のアプリを使って会員登録をすると、ベビーシッターの検索と依頼、利用料金の支払いまでを一括で行えるので、忙しいママにも利用しやすいサービスといえるでしょう。いざというときの子どもの預け先のひとつとして、キズナシッターの利用登録から始めてみてはいかがでしょうか。
働く忙しいママの味方!調理済み冷凍幼児食mogumo(https://mogumo.jp/)の宅配サービスもおすすめ」

忙しい毎日の中で、栄養バランスや食べやすさ・おいしさを考慮しながら食事を用意することは、なかなか難しいですよね。
そんな時は、mogumoの幼児食冷凍宅配サービスがおすすめです。
mogumoは、調理済みの幼児食が冷凍で配送されるので、温めるだけですぐに食べられます。献立を考えたり調理したりする手間を減らせますよ。
メニューは管理栄養士監修で、栄養バランスも考えられており、幼児期に必要な栄養素をカバーできるものが揃っています。
ぜひ活用してみてください。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。