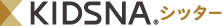年子の育児で大変なことは?ママやパパたちが工夫したことや利用したサービス

年子の育児が大変だと感じるとき
年子の子どもがいる家庭のママやパパたちに、年子ならではの大変だと思うことを聞いてみました。
「私は子どもたちと毎日お風呂に入る度に大変だと感じています。お風呂からあがった後も、自分の身支度を後回しにして子どもたちの着替えを手伝ったり髪を乾かしたりしているので、一息つく間もありません。」(20代/2歳児と3歳児のママ)
「下の子をベビーカーに乗せ、上の子と歩いて外出するとき、上の子もベビーカーに乗りたいと言うことがありました。兄弟でベビーカー取り合いになってしまうと、まだ幼い上の子が我慢することが増えてしまい、年子の育児は大変だと感じます。」(30代/1歳児と2歳児のパパ)
年子の育児は、兄弟の年齢が近いことからママやパパにして欲しいことが同じだったり、1つしかないものを欲しがったりすることもあるようです。上の子と下の子の生活リズムの違いや、別々に食事や寝かしつけをすることに大変さを感じているママもいました。
年子の育児をサポートは誰にお願いしているのか

iStock.com/paylessimages
「子どもたちのことを一番理解している夫から、子育てのサポートをしてもらいたいと考えました。帰宅した夫に子どもたちをお風呂に入れてもらったり、子どもと遊んでもらったりしてくれると、私はその間に家事に集中できるので助かります。」(30代/2歳児と3歳児のママ)
「うちの場合は近所に私の両親が住んでいるので、母に下の子のお世話をしてもらったり、上の子の遊び相手をしてもらっています。」(30代/3歳児/4歳児のパパ)
「夫婦どちらの実家も遠方なため、誰かに育児を手伝って欲しいと感じたときは行政や民間の子育て支援サービスを利用しています。」(40代/3カ月の赤ちゃんと1歳児のパパ)
子育てのパートナーであるパパと協力している家庭や、祖父母にサポートをお願いしている家庭がありました。
近くに頼れる相手がいない場合、行政や民間の子育て支援サービスを利用したいと考えるパパもいました。自治体のホームページなどから、どのようなサポートを受けられるかを確認するとよいかもしれません
ママやパパたちが利用した事業やサービス
年子の育児をしているママやパパたちが、実際に利用した子育て支援事業やサービスをご紹介します。
保育園の一時預かり事業
「下の子を出産するときに、保育園の一時預かりを利用しました。産前から産後まで利用できたので、産前は体調に合わせてゆっくりと家事や入院の準備を、産後は下の子のお世話や自分の体を休める時間を作りやすかったです。」(40代/5カ月の赤ちゃんと1歳児のママ)
他には、一時保育は、就労以外にもリフレッシュなどを目的とした利用もできるようなので、年子育児に疲れを感じたときに利用しているというママの声もありました。
ファミリー・サポート・センター
「ファミリー・サポート・センターを利用して子どもを預かってもらっています。どちらか1人の子どもといっしょに病院へ受診する予定があるときは、事前に予約して1人の子どもを預かってもらいました。」(30代/8カ月の赤ちゃんと1歳児のママ)
ファミリー・サポート・センターは、育児をサポートして欲しい人と、お手伝いしたい人がそれぞれ会員となり、地域のなかで助け合うといった自治体が運営する事業です。
ベビーシッターサービス

iStock.com/poligonchik
「我が家では月に2回程度ベビーシッターの方に下の子を預かってもらい、私は上の子と遊んだりお出かけしたりとゆっくり過ごす時間を作っています。(20代/4カ月の赤ちゃんと1歳児のママ)
普段から赤ちゃんや子どもに慣れているベビーシッターの方になら、安心して預かってもらえるかもしれません。ベビーシッターにはマッチングサービスもあり、希望の時間にシッティングしてもらいやすいところも、ママやパパにとって利用しやすいといえるでしょう。
年子育児をするときの工夫
年子の育児が大変だと感じるとき、どのような工夫があるのか知りたいママやパパもいるのではないでしょうか。ママやパパたちに、年子育児の工夫を聞いてみました。
便利グッズを活用する
「上の子の体を洗っている間、つかまり立ちを始めたばかりの下の子の様子が気になったのでバスチェアを用意しました。下の子から目を離すときはバスチェアを使うと、上の子や自分の体を洗うときも安心です。」(30代/10カ月の赤ちゃんと1歳児のパパ)
「下の子には抱っこ紐を、上の子にはベビーカーを使ってお出かけしていましたが、2人ともベビーカーに乗りたいとせがむときがありました。ベビーカーの後ろ側にステップを取り付けると、上の子もベビーカーに乗った状態で移動できるので満足したようです。」(30代/1歳児と2歳児のママ)
食事の介助が大変だと感じるパパのなかからは、下の子にはポケットつきのエプロンを、上の子には底にシリコン素材が使われた倒れにくいコップや食器を使うことで食べこぼしが気になりにくくなったという声も聞かれました。
子どもの気持ちに寄り添う
「下の子が生まれてから、上の子が我慢するシーンが増えたように感じました。まだ幼い上の子の気持ちに寄り添いたいと思い、上の子が甘えてきたときは抱っこなどのスキンシップを取るよう心がけています。」(20代/8カ月の赤ちゃんと1歳児のママ)
「うちの子たちは、年齢が近いせいか何をするにも競い合い、ときにはケンカをすることもあります。それぞれの子どもと過ごす特別な時間を作ったり、大好きだということを伝えたりして子どもの気持ちに寄り添いたいと思いました。」(30代/7歳児と8歳児のパパ)
育児が大変だと感じたときこそ、子どもの気持ちに寄り添ってあげたいと考えるママやパパの声がありました。子どもの年齢やシーンに合わせて、どちらかの子どもが我慢することが増えないように心のケアをするとよいかもしれません。
家庭に合ったサポートや便利グッズを活用しよう

iStock.com/kyonntra
年子の育児をしていると、年齢が近いことで大変さを感じるというママやパパもいるようです。夫婦や家族で協力する他にも、行政や民間の子育て支援サービスに依頼するのもよいかもしれません。誰にどのようなサポートして欲しいのかを夫婦で相談し、必要なサポートや便利グッズも活用しながら年子の育児を楽しめるとよいですね。
同時に3人までシッティングできる「キズナシッター」におまかせ
「年子の育児と家事で疲れてしまった」「少しの間だけでも子どもを預かって欲しい」というママやパパもいるかもしれません。年子の育児をしている家庭をサポートするサービスのひとつとして「キズナシッター」を利用してみてはいかかでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士・幼稚園教諭・看護師いずれかの資格所有者です。同時に3人までの子どもの預かりが可能なので、年子の子どもとは別に年の離れた子どもがいるという家庭にもご利用いただけます。
キズナシッターは専用アプリを使うことで、会員登録から利用料金の支払いまで一括で行なえます。年子育児の疲れたときの子どもの預け先のひとつとして、キズナシッターの登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。