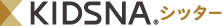子どもの預け先がない!急用や仕事の際に活用したい一時預かりサポート

「子どもの預け先がない」という親の悩み
 kimi / stock.adobe.com
kimi / stock.adobe.com
子育て中のママやパパのなかには、「上の子が通う園の行事に参加したいが、下の子の預け先がない」「悪天候を理由に学校が休校になって、子どもの預け先がない」という経験をしたことがあるという方もいるのではないでしょうか。
共働き世帯が増え、育児と仕事を両立する家庭が増えている今、このように「子どもを預けたいのに、子どもの預け先がない」と困ったことがあると、多くのママやパパが悩んでいるようです。特に、仕事が休めないときは、どう対処しようかと、頭を抱えてしまいますよね。
今回の記事では、そんなときに、どのような子どもの預け先があるかを、いくつかピックアップして紹介します。
子どもを預かってほしいシーン
まずは、どのようなときに子どもを預かってほしいと思うのか、子どもの預け先が必要なシーンについて、ママやパパに聞いてみました。
通院したいとき
多くのママやパパが、通院時に子どもを預けたいと感じているようです。なかには、2人目や3人目など下の子の妊婦健診時は、検査項目が多くなることもあるため、子どもを預けてゆとりを持って通院したいというママの声もありました。
園や小学校で行事があるとき
上の子が保育園に通っている場合、園の行事に出席するときに下の子を預けたいと考えるパパの声です。ほかにも、園や小学校の運動会や遠足では、屋外で下の子のお世話をするのは大変だと感じ、誰かに預かってもらえると助かるというママの声もありました。
子どものクラスや学校が休みになったとき
感染症などが流行り、クラスが休校になって、子どもの預け先に悩んだというママの声もありました。急に学校がお休みになると、早急な対応を迫られて戸惑うママやパパは多いかもしれません。
仕事を始めたいとき
仕事を始めるタイミングに、入園先となる保育園の空きが見つからないこともあるようです。待機児童が少ないといわれる自治体でも、年度の途中だと希望する園に空きがない場合もあるでしょう。そのため、入園先が見つかるまでの期間、子どもを預かってほしいと考えるママも少なくないかもしれません。
用事があるとき
親族や友人の冠婚葬祭に、子どもの預け先がなく困ったというママがいました。ほかにも、上の子の七五三でスタジオでの撮影予約をしたとき、下の子のお昼寝と重なる時間だったので、生活リズムを大切にしたいという考えから下の子の預け先を探したというパパの声もありました。
子どもの預け先
 Krakenimages.com / stock.adobe.com
Krakenimages.com / stock.adobe.com
ママやパパたちはさまざまなシーンで、子どもの預け先に悩んでいるようです。では、実際に何らかの事情で子どもを預けたいとき、どのような子どもの預け先を利用できるのでしょうか。いくつかピックアップして紹介します。
保育園の一時保育
一時保育の利用目的は、就労以外にリフレッシュなどでもよいようなので、育児に疲れを感じたときに利用しているというママの声もありました。保育園によっては、休日保育として週末の土曜や日曜に子どもを預かってもらえることもあるようです。
学童保育
学校が臨時休校中でも、民間の学童などでは学童保育の受け入れを継続するケースもあるそうです。一方で、小学校の休校中は同様に閉所する施設もあるそうなので、いざというときのために、事前に利用している施設に確認しておくと安心かもしれません。
病児・病後児保育
病児・病後児保育とは、子育てと就労の両立支援の一環として、保育園などに通っている子どもが病気や怪我で集団保育が難しい場合に、専用施設で一時的に預かる保育サービスです。病児保育は罹患中、病後児保育は回復期に利用できます。病院や自治体、保育園などさまざまな施設で運営されているようなので、近隣施設の場所や利用料金などをあらかじめ確認しておくとよいかもしれません。
なお、これらのサービスを利用するには、事前の登録手続きや、実施施設への連絡、かかりつけ医の受診などが必要となる場合がほとんどのため、注意しましょう。
ショートステイ
子どものショートステイ事業とは、保護者が疾病・出産などによる入院、出張、冠婚葬祭、育児不安や育児疲れ、看病疲れなどで、家庭で子どもの養育が一時的に困難となったとき、子どもを施設で預かることです。対象となる子どもの年齢や、利用期間、費用などは自治体によって異なるため、事前に確認しておくとよいでしょう。子どもといっしょの事前面談があったため、安心して預けられたというママの声もありました。
トワイライトステイ
トワイライトステイ事業は、保護者が仕事や、そのほかの理由により、平日の夜間、または休日に不在となり、子どもの養育が困難となった場合などに、児童養護施設など保護を適切に行うことができる施設で子どもを預かるものです。前述の「ショートステイ」との違いは、基本的に宿泊を伴うかどうかにあるようです。利用要件や利用方法などは、こちらも自治体によって違いがあります。事前にしっかり確認しておきましょう。
夫婦の両親
近くに両親が住んでいると、急に子どもを預けたいときもすぐに対応できて助かりますよね。なかには、両親に自宅に来てもらって子どもをみてもらったというママもいました。親族であれば、子どもにとっても安心できるかもしれません。
ファミリー・サポート・センター
自治体が運営するファミリー・サポート・センターを利用した家庭もあるようです。これは、地域のなかで支援を受けたい方とサポートをしたい方がそれぞれ会員登録し、子どもの預かりなど相互援助活動を行う事業です。普段からよく利用しているため、子どもが会員の方に懐いていて利用しやすいというパパの声もありました。
ベビーシッターサービス
上の子との時間を大切にしたいとき、ベビーシッターサービスに下の子のお世話を依頼したというママの声もありました。シッティングの対象年齢はベビーシッター会社によってそれぞれ異なるようですが、おおむね0歳から12歳までの子どもを対象としているところが多いようです。サービス内容もさまざまなため、事前にどのようなシッティングをしてくれるのか確認しておくとよいでしょう。
なお、実際に当ベビーシッターサービス「キズナシッター」を利用した方の体験談についてはこちらで紹介しています。
出典:一時預かり事業/こども家庭庁 出典:子育て短期支援事業について/こども家庭庁 出典:ファミリー・サポート・センター事業/厚生労働省子どもを預けるときに準備したこと
 metamorworks / stock.adobe.com
metamorworks / stock.adobe.com
実際に子どもの預け先を検討するとき、どのような準備をしておくとよいのでしょうか。ママやパパたちに、子どもを預けるときに準備したことを聞いてみました。
利用登録をしておく
子どもの預かりサービスには、事前登録や会員登録が必要なものも少なくないようです。いざというときに、利用日の申請がしやすくなるよう、予定がない場合でも登録を済ませておくとよいかもしれません。
なお、キズナシッターでは、保育士や幼稚園教諭、看護師などの国家資格所有者が0歳~12歳までのお子様をお預かりいたします。事前に登録しておくと、急な依頼にも対応可能です。
登録の詳細はこちらをご覧ください。
お世話グッズを用意する
普段、使い慣れている育児アイテムを使用した方が子どもにとっても安心できるでしょう。お世話グッズを用意するとき、どこに何が入っているのかがすぐにわかるよう、メモを添えたというパパの声もありました。
緊急連絡先を伝える
何かあったときのために、ママとパパの緊急連絡先を伝えておくことも大切かもしれません。パパのなかからは、すぐに連絡があったことに気付けるように、マナーモードにした携帯電話をジャケットの内ポケットに入れていたという声も聞かれました。
子どもの預け先がない!とならないために
今回は、さまざまなシーンに応じて利用できる、子どもの預け先をピックアップしてお伝えしました。
育児中の方の多くが「子どもの預け先がない」と困ったことがあるようです。いざというときのために、普段から子どもの預け先の候補を複数持っておくことは、自分たちの生活を守るためにも必要なことかもしれません。
仕事や急用で、「子どもの預け先がない!」と焦ることがないよう、事前登録や面談など、今できることからはじめてみてはいかがでしょうか。
同時に3人までシッティング可能な「キズナシッター」の活用を
「子どもを預かって欲しい」「同時にきょうだいを預かってくれるベビーシッターサービスを利用したい」という家庭もあるかもしれません。
そんなときは、「キズナシッター」にご相談ください。
キズナシッターは、登録しているベビーシッター全員が、保育士や幼稚園教諭、看護師といった資格所有者です。0歳の赤ちゃんから12歳の子どもを対象としています。同時に3人までのシッティングが可能なため、3兄弟(姉妹)を預かってほしいという希望にも対応可能です。
専用のアプリを活用し、会員登録やベビーシッター検索、利用日の依頼から支払いまでを一括で行えるのも、魅力のひとつでしょう。
会員登録や年会費などに費用は一切かからないため、いざというときの預け先のひとつとしてこの機会にぜひご検討くださいね。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。