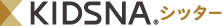【体験談】産後の外出はいつから?赤ちゃんと外出するときに気をつけたことなど

産後の外出はいつから始めていた?
産後のママは、出産という大仕事を終え、ゆっくり体を休める大事な時期でもあります。
そのなかで、いつから外出してよいのか悩む方もいるかもしれません。
出産後、ママたちは外出をいつから始めていたのか体験談とともに紹介します。
赤ちゃんの1カ月検診を区切りに
「出産した産院で赤ちゃんの1カ月検診があったので、その検診を区切りに、少しずつ私も外出したり、体を動かし始めました」(30代/6カ月のママ)
赤ちゃんの様子に応じて、外出のタイミングを図るママもいるようです。
赤ちゃんの1カ月検診をきっかけに外出を始めたママのなかには、上の子どもの保育園の送り迎えもその時期を堺に、少しずつママが担うようにした方もいました。
体調が良くなってから
「出産後は、慣れない授乳や赤ちゃんのお世話になかなか体調が回復しなかったので、産後2カ月ほどしてから、外出するようになりました」(20代/10カ月のママ)
出産後1カ月は、体を休ませることに専念したママの声が聞かれました。
産後は、体を休ませることと合わせて、赤ちゃんのお世話も加わるため、ママの体調の回復には個人差もあるようです。
外出はママの体調をみて行うことも大切でしょう。

Africa Studio/shutterstock.com
赤ちゃんと外出するときに気をつけたこと
赤ちゃんとの外出は、家の中とは違いさまざまなことが心配になるママもいるかもしれません。
赤ちゃんとの外出にはどのようなことに気をつけたのかママたちの体験談を紹介します。
移動はなるべく短時間に
「チャイルドシートに座わらせるのも短い時間がよいと思い、移動はなるべく短時間にしました。
出かけた先でも、あまり長居はせず、気分転換になる程度にしておきました」(40代/11カ月のママ)
赤ちゃんにとって、外出は刺激も多く、長時間の外出は疲れてしまうこともあるようです。
そのため、赤ちゃんの機嫌や体調を最優先にして、泣いたりクズってしまうことがあった場合には、早めに用事を済ませて帰宅できるよう対応したママもいました。
人の多い場所を避ける
「出かける際は、感染症など気になることが多かったので、なるべく人混みを避けて外出をしました。
スーパーマーケットに行くときも、混む時間帯を避けるようにしました」(20代/7カ月のママ)
特に冬場など感染症の気になる時期は、人の多い場所を避けて外出する声が多く聞かれました。
赤ちゃんのお世話をする側も、体調を崩さないようマスクをするなど予防に努めるように心がけたという方もいました。
直射日光や気温の変化に気をつける
「車やベビーカーでは、日差しよけを使ったり、冷房が効いている場所ではブランケットを使い、寒さ対策をしました。
大型ショッピングモールに行った際は、ショッピングモールのベビーカーを使うことが多かったですが、そのまま寝かせるのは硬かったり、冷たいかなと思い、バスタオルを敷いてから寝かせていました」(30代/9カ月のママ)
外出の際は、直射日光や外気が気になるものですね。
バスタオルやブランケットを持参して、赤ちゃんの体温調節をした方のなかには、ガーゼ状の大判のブランケットを1枚持っていると、赤ちゃんにかけたり、オムツ替えのときなど、さまざまな場面で重宝したという声が聞かれました。
ママが一人で外出したいときの対応策とは
産後は、慣れない子育ての中で一人の時間を持ちたいと感じたり、どうしてもママ一人で外出しなければならない場合もあるのではないでしょうか。
ママが一人で外出したいときにどのように対応していたか、ママの体験談とともに紹介します。
パパに子どもを預け、短時間の外出
「産後は、赤ちゃんとゆっくりすごせることに、幸せも感じていましたが、1カ月を過ぎたあたりから、ちょっと出かけたいな思うようになりました。
夫が休みの日に、子どもが寝ているときや機嫌がよいタイミングを見て、短時間の外出を楽しみました」(40代/1歳のママ)
パパが仕事のときは、どうしても子どものお世話を一人で担うことが多いママも、休みの日はパパに赤ちゃんをお願いして、僅かな時間でも外出をして気分転換をした方もいるようです。
パパにとっても、一人で赤ちゃんを預かることは緊張感もありますが、二人だけの時間に新鮮さを感じることもあるようです。
両親や義父母に預ける
「義父母が近くに住んでいたので、困ったときには声をかけてねと言われていたこともあり、買い物や病院に行きたいときに、お願いをしました。
義母も、赤ちゃんを見ているのは飽きないわねと言って、快く預かってくれたので助かりました」 (20代/7カ月のママ)
パパが仕事のある平日や忙しくて預けられない場合には、近くに両親や義父母が住んでいると、いざというとき頼もしいものですね。
一人で赤ちゃんを一日見ているより、両親や義父母がいる環境で赤ちゃんのお世話をすると、赤ちゃんの普段と違う表情や育児について知識など、新鮮な発見もあるかもしれません。
ちょっとした時間でも気分転換になりそうですね。
ベビーシッターや自治体の預かりサービスの活用
「うちの場合は、夫は仕事が忙しく、両親や義父母は近くに住んでいないので、なかなか外出のタイミングがなく、ストレスが溜まっていました。
そんなとき、友人にベビーシッターサービスにについて話を聞き利用してみました。
私が出かけているときの赤ちゃんの様子も詳しく教えてもらい、とても良かったです」(30代 10カ月のママ)
近くに頼れる存在がいない場合、ベビーシッターや自治体の預かりサービスを活用するのも一つの方法かもしれません。
赤ちゃんと2人だけの生活は、孤独に感じることもあり、ベビーシッターに来てもらうことで、わが子について共感してくれる存在がパパ以外にもでき、嬉しかったというママもいました。

Shinya nakamura/shutterstock.com
産後の外出は無理をせず、体の調子をみながら少しずつ
産後の外出について、いつから外出を始めたか、赤ちゃんとの外出に注意した点や、ママが一人で外出したいときの対応法について体験談とともに紹介しました。
外出する際には、長時間歩いたり重い荷物を持つなど、体に負担になるようなことは避け、リフレッシュする気持ちで、無理せず体の様子を見ながら少しずつ始めてみることが大切なようです。
産後は慣れない子育ても加わり、気分が沈むこともあるかもしれません。
上手に周囲に頼り、気分転換ができるとよいかもしれませんね。
産後の外出に、子どもを安心して預けられる「キズナシッター」
生後数カ月の子どもを預けて外出することは、ママにとっては不安な気持ちがあるかもしれません。
そのようなときには、子どもを安心して預けられる「キズナシッター」を活用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士資格、看護師資格など子どもに携わる資格保有者100%のベビーシッターサービスです。
そのため、生後数カ月の赤ちゃんであってもしっかりとした知識とともに、経験豊富なベビーシッターがサポートしてくれます。
ベビーシッターの活用は、ママの外出時に利用するだけではなく、ママが自宅にいるときでも、赤ちゃんの沐浴のサポートをしてもらったり、赤ちゃんのお世話をしてもらっている間に、ママはゆっくりすごすなど活用方法はさまざまです。
担当するベビーシッターは、自己紹介ページや利用者のレビューを参考に自分で決めることができ、事前に面談することでベビーシッターとの相性を確認してから、シッティング依頼をすることも可能です。
アプリに登録することで、自宅にいながらベビーシッター選びから、シッティング依頼、利用料の決算までできるので、ママにとっても負担が少ないでしょう。
赤ちゃんの預け先に悩んだときや、育児のサポートをしてもらいたいと感じたときには、気軽にキズナシッターを活用してみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。