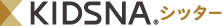共働き家庭のワンオペ育児。仕事と家事、子育ての両立方法

仕事をしながらのワンオペ育児の悩み
仕事をしている中での「ワンオペ育児」。
時間に余裕が持てなかったり、職場に後ろめたさを感じていたりとあらゆる悩みを抱えている方も多いでしょう。
ここでは、共働き家庭におけるワンオペ育児の悩みを体験談とあわせて紹介します。
毎日バタバタしていて時間がない
「毎日、慌ただしく子どもを保育園に送り届け、仕事が終わったらすぐにお迎えに行き、急いでご飯を作って…とバタバタとしていて、家事や子育てをしっかりやりたいと思いますが時間がありません。
夫は仕事で忙しいので、ワンオペ状態で辛いです」(30代ママ 3歳児ママ)
共働きの場合、パートナーの協力が得られないと家事や育児をすべて一人で行わなければいけません。
育児は待ったなしなので、「お腹が空いた」や「もっと遊んで」など、その都度子どもの要求にも応えているとあっという間に時間が過ぎてしまいます。
そのため、子どもとゆっくり遊ぶ時間を作ったり、掃除を毎日行うなどのまとまった時間を確保できないこともあり、思うようにできず悩みを抱える方もいるようです。
仕事を休むことに気を使う
「職場には、育休で長期間休んでしまったので、復帰してからはなるべく迷惑をかけたくないと思っていたのですが、子どもはよく熱を出したり感染症になり、会社を休まなければならない日も多いです。
私の両親は仕事をしているので、お願いすることも難しい状態です。
子どもに何かあったときは、私が対応するように暗黙の了解になっているので主人に頼ることもできません」(20代ママ 1歳児と4歳児のママ)
子どもは突然熱を出すことも多く、保育園や学校に通っている場合は、集団生活をしているので感染症にかかるリスクも高いです。
仕事をしているなかでの早退や欠勤はできれば避けたいことですが、両親やパートナーを頼れない場合には難しいことも多いようです。
子どもがいることを職場が理解していても、頻繁に仕事に迷惑がかかると後ろめたさを感じてしまう方もいるでしょう。
気持ちにゆとりがもてない
「うちでは、ほぼ家事や子育ては私が行っているのでワンオペ状態です。
家計のために仕事を続けていますが、思い通りに進まない育児や周囲に悩みを相談できる人がいないと不満が溜まり、気持ちに余裕が持てません」(30代ママ 5歳児のママ)
ワンオペ育児をしている方の中には、仕事と家事・育児の両立に悩む方も少なくないようです。
家族のためにと仕事を続けていても、毎日慌ただしいなかで気持ちにゆとりがもてず、「些細なことで子どもをつい怒ってしまい悩んでいる」という声も聞かれました。

metamorworks/shutterstock.com
ワンオペ育児を乗り越えるための働き方の工夫
共働き家庭にとって、ワンオペ育児を乗り越えるために「働き方」を少し変化させることもひとつの方法かもしれません。
ここでは、働き方の工夫を紹介します。
時短勤務制度を使う
子どもを持つ働くパパやママのために、仕事と育児の両立ができるようにさまざまな制度があります。
その中のひとつに「時短勤務制度」というものがありますが、これは、子どもが3歳になるまで1日おおむね6時間の勤務に変更することができるというものです。
会社によっては、取得できる年齢が3歳以降も継続できる場合もあるようです。
働き方を少しゆるくすることで、時間的な余裕がうまれ、その分慌てずに家事に取り組めたり、子どもの話にゆっくり耳を傾けられることもあるかもしれません。
出典:短時間勤務制度(所定労働時間の短縮等の措置)について/厚生労働省
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/navi/manual/doc/attention.pdf
業務の効率化や見える化
仕事をしている方にとって、残業は悩みの一つなりますね。
保育園や学童のお迎えに間に合うよう定時に上がらなければならないために、その日は仕事が終わらず次の日にしわ寄せがいったり、他の方に仕事をお願いして退勤した経験がある方もいるかもしれません。
そのような悩みを抱えているときには、限られた勤務時間の中で、効率よく仕事をしていくために、業務の効率化や見える化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
例えば、出勤したら「今日やらなければならない仕事を書き出してみる」。
これは、仕事の見える化となり、ひと目でやるべきことが把握できます。
終わった業務をリストから消していけば、片づいていると実感できるでしょう。
効率的に仕事を進めていくために「この、スキマ時間でこっちの業務をしておこう」など時間を有効に使うこともできるかもしれません。
結果的に、仕事内容を効率よく進めることができ、仕事を気持ちよく終わらせ定時に上がれるようになったという声もありました。
在宅勤務ができるか会社に相談をする
デスクワークなど勤務内容によっては、在宅で仕事ができる場合もあるかもしれません。
そのようなときには、会社に働き方について「在宅勤務に変更できるか」相談してみるのも一つの方法でしょう。
在宅勤務が可能になると、会社までの移動時間が実質的になくなるので、余裕をもって仕事ができたり、移動時間が自由な時間に変わります。
その時間を利用して、途中になっていた家事を済ませてしまったり、自分の時間としてリフレッシュすることもできます。
在宅勤務に変更したことで、天候や交通状況に左右されることも減り、移動時間のストレスの軽減になったという意見も聞かれました。
ワンオペ育児を乗り越えるための家事や子育ての工夫
ワンオペ育児では、家事や子育ての中でも多くのことに追われます。
ここでは、ワンオペ育児を乗り越えるための子育ての工夫を紹介します。
手を抜けるところは抜いて気持ちの余裕をもつ
仕事をしながら、育児や家事とすべてのことを毎日こなしていくことはとても大変です。
手を抜けるところは抜いて気持ちの余裕をもてるとよいでしょう。
例えば、食事はいちからすべて手作りと決めてしまうと、今日は何を作ろう…と献立作りから頭を抱えてしまいます。
ときには、スーパーマーケットのお惣菜コーナーでメインのおかずは購入し、家で作るのはお味噌汁と野菜を切って副菜にするなど。
すべてを全力でやろうとがんばるのではなく、手を抜けるところを上手に見つけて、子どもとの時間をすごせると子どもも嬉しいですね。
パートナーと家事や育児を分担をする
ワンオペ育児の大きな要因は、夫婦のどちらか一方に家事や育児の負担が大きくなっていることです。
パートナーと家事の分担をすることも大切でしょう。
しかし、仕事内容や勤務時間によっては家事の分担が難しいこともあるかもしれません。
まずは、お互いの状況を知るために、家事や子育てで行っていることを思いつくままに書き出してみてはいかがでしょうか。
お互いが、どのようなことをしていて、どんなことを大変だと感じているのか知ることから始めてみましょう。
普段、家事や子育てについて話したことがないご家庭では、相手が負担と感じていることさえ知らなかったという場合もあるようです。
家事や子育ては、場合によっては苦手なこともあるので、夫婦で話をしながら、少しずつでも分担ができる形を作れるとよいかもしれません。
片づけしやすい工夫をする
家事の中では、子どものおもちゃの片づけも問題の一つになります。
子どもが言葉を理解できるような年齢なってきたら、片づけを率先してやってくれるように、お片づけのハードルを下げることもひとつの方法です。
例えば、おもちゃの種類ごとにケースを作り、ケースにはおもちゃの写真を貼っておくと、子どもはどこに何を片づければよいかひと目でわかるようになります。
最初は、声をかけながらいっしょに片づけることも必要ですが、慣れてくると「このおもちゃはこのケース」とわかるようになり、進んでやってくれるようになるでしょう。
「片づけなさい!」と何度も言わなくても、子どもが自ら行動してくれると、親は成長を感じるとともに、気持ちの余裕も生まれるかもしれません。
お片づけに限らず、子どもができることは、どんどん自分でできるような工夫をすると家事が一気に楽になるかもしれません。
ベビーシッターなどのサービスを活用
近年では、「ベビーシッター」や「家事代行サービス」など子育て家庭をサポートするさまざまなサービスが充実しつつあります。
共働き家庭の中には、上手に代行サービスを活用して、自分の時間や家族の時間を作っている方もいるようです。
例えば、ベビーシッターを利用している方の中には、仕事が忙しい時期は、バタバタする朝の時間帯にサポートに来てもらい、朝食を食
べさせてもらったり園の送迎をお願いするという利用の仕方をしている方もいます。
仕事との両立を考えたとき、すべてを自分でやらなければと考えるのではなく、ときにはプロの力を借りて時間の余裕をもつことで、気持ちのゆとりが生まれることもあるかもしれません。

Keisuke_N/shutterstock.com
仕事をしている中でのワンオペ育児、工夫できる糸口を見つけよう
今回は、共働きのワンオペ育児について、悩みの体験談やワンオペ状態を乗り越える「働き方」と「家事や子育て」の工夫を紹介しました。
仕事をしている責任感と、家事や育児に追われる日々は休まることがなく、余裕がもてないことも多いかもしれません。
ときには、ベビーシッターなど代行サービスを上手に使い、自分の時間を積極的に作ってみてはいかがでしょうか。
夫婦での会話を大切にしながら、お互いに仕事をしている姿を労い、家事をやってもらったときには感謝の気持ちを伝え合えると嬉しいものです。
いっしょに「仕事・家事・育児」を乗り越えていけたらよいですね。
子どもを安心して預けられるサービス「キズナシッター」
ワンオペ育児に悩んだときには、子どもを安心して預けられる「キズナシッター」を利用してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士や幼稚園教諭など100%資格保有者となり、専門知識をしっかり持った経験豊富なベビーシッターが多く登録しています。
利用は専用のアプリを使い、ベビーシッター選びから利用料の決済まで完了するので、仕事をしている中でも活用しやすいでしょう。
年会費や会員費は一切かからず、勤め先の福利厚生サービスを利用することも可能です。
アプリの登録は無料なので、気軽に登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
お住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。