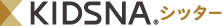産後クライシスになりやすい人の特徴と乗り越えたママパパの対策方法

産後クライシスとは
「産後クライシス」とは出産後にさまざまな変化が起こり、夫婦関係に亀裂が生じることを意味します。一般的には、産後数年間が産後クライシスに陥りやすい時期といわれています。
なかには子育てに追われて配偶者への愛情が冷めてしまったり、意見が食い違って喧嘩が増えてしまったりすることがあるでしょう。
「子どもが産まれ、これから協力して子育てをしていこう」という夫婦にとっては、避けたい状況ですよね。
そもそも、産後クライシスになりやすい人にはどのような特徴があるのか、妻・夫ともに性格的な部分と、産後に陥りやすい要因にフォーカスしてそれぞれの特徴を見ていきましょう。
【妻の場合】産後クライシスになりやすい人の特徴

育児やプレッシャーから産後クライシスになりやすい人の性格・傾向や要因について、ママたちの声を集めました。
性格・傾向
真面目で完璧主義
真面目でなんでも完璧にこなしたいという考え方は、産後クライシスになりやすい人の特徴のひとつと言えるかもしれません。
このようなタイプは、自分の理想や計画が崩れると強いストレスを感じやすい傾向があるようです。育児では予測不能なできごとが多いため、自分で全てを抱え込んでしまうと負担が大きくなります。
配偶者にも理想を押しつけることで夫婦間の摩擦が生じる場合があるため、考え方や物の見方にも柔軟性を持てるよう気をつけるようにしたというママの声もありました。
他人と自分を比較しがち
他人と自分を比較して「どうしてみんな普通に子育てできているの?上手くいかないことがたくさんある」と不安を抱いてしまいがちな方は産後クライシスになりやすいかもしれません。
その原因が「配偶者にあるのでは?」と考え始めると、次第に相手の嫌な面ばかりが目につくようになって関係も悪くなりそうです。
他人と比較してしまう人は、「自分だけができていない」と感じることで自信を失いやすい傾向にあるようです。そうならないように、SNSはいいところだけを切り取って見せているだけ、と割り切って見るようにしているというママの声もありました。
このストレスが配偶者への不満につながり、夫婦間の関係が悪くなってしまったというママの声も。他人との比較を避け、自分たちのペースで育児に取り組めるよう気持ちを切り替えられるとよいかもしれませんね。
自立心と自己犠牲が強い
自立心が強く「自分が頑張れば何とかなる」と考える人は、知らず知らずのうちに負担を抱え込みがちです。また、自己犠牲の意識が強いことで、配偶者に頼ることが「迷惑をかける」と思い、助けを求めにくくなることもあるようです。
この状態で赤ちゃんの育児を続けるのはとても危険かもしれません。ママが心身のバランスを崩し、夫婦関係にも悪影響を及ぼすことも少なくないでしょう。適度に周囲の助けを受け入れることが、夫婦関係の安定に繋がります。
要因
初の育児で不安なことが多い
初産での子育てははママにとってはじめてのできごとの連続です。「赤ちゃんが泣き止まない」「完全母乳で育児できないと母親失格?」など、ちょっとしたことでさまざまな不安を抱いてしまったというママの声は多くありました。
妻がマンツーマンで赤ちゃんのお世話にかかりきりになると、精神的にも視野が狭まり不安定になることがあるようです。結果的に夫に対して攻撃的になることや、イライラがおさまらないといった状況になりそうです。
この状況が解消されないと、夫のサポート不足や無関心に対して過剰に反応することもあるでしょう。お互いに気持ちを共有し、育児の悩みをともに乗り越える意識が必要とされるでしょう。
悩みを相談できる人がいない
育児で悩みを抱えたときに誰にも相談できる人がいないと、その不安やいらだちを配偶者にぶつけてしまうこともあるでしょう。
また、悩みを抱えても「自分で解決できることだから」と一人で抱え込んでしまう性格だと、夫婦で協力する機会を少なくさせる悪循環にもなりそうです。
友人など頼れる相談相手がいないと、育児の悩みやストレスが蓄積しやすくなります。これが配偶者への不満として現れると、夫婦関係の亀裂につながる場合があるかもしれません。
ホルモンバランスの変化
産後はホルモンバランスが大きく変化するため、感情が不安定になりやすい時期です。この変化は産後うつを引き起こすこともあるため、適切なサポートが重要です。
妻自身が感情の波をコントロールできない場合、夫婦間でのトラブルが増えることがあります。夫は妻の状態を理解し、精神的なケアを心掛けることが大切です。また、必要に応じて婦人科やカウンセリングなど専門家の助けを借りることも考えましょう。
【夫の場合】産後クライシスになりやすい人の特徴

産後クライシスになりやすい・ひきおこしやすい要因は妻の問題だけではありません。夫婦間の問題である以上、育児や家事にどう向き合うか、夫の特徴も大きく関係するでしょう。
性格・傾向
仕事や趣味に没頭する
仕事や趣味に没頭する夫は、育児や家事への関与が少なくなり、妻の負担が増える原因になりがちです。
妻が孤独感を覚えると、夫婦間のコミュニケーション不足に発展しやすくなります。仕事や趣味も大切ですが、産後の時期は家庭内での役割をしっかり意識し、家事や育児に積極的に関わる姿勢が求められるでしょう。
家庭外の人間関係を優先する
特に子どもが小さいうちや、妻が産後の育児で不安定になっている場合、家庭より個人的な人間関係を優先する夫は、育児における妻の孤独感を強める要因になるでしょう。
妻は「子どもが生まれても自分だけが負担を抱えている」と感じやすく、夫婦関係の悪化に繋がることがあります。
家庭外に向ける自己顕示欲よりも、育児は夫婦で協力するものであるという意識を持って家庭を優先するように考え方をシフトしてみましょう。
共感力・ストレス耐性が低い
共感力が低く、ストレス耐性が弱い夫は、産後の変化や妻の負担を十分に理解できず、トラブルが生じやすい傾向があります。
育児のストレスを共有する姿勢がないと、妻の不満が蓄積しやすくなります。小さな不満でも夫婦間で率直に話し合い、共感しあう姿勢を持たないと、信頼関係を築くことができないでしょう。
先輩パパの中には、赤ちゃんの泣き声がストレスなので育休中の妻に育児を丸投げしていたら、子どもが成長して手がかからなくなった頃に、妻が子どもに関わらせてくれなくなったという声が聞かれました。
要因
家事・育児への関わり方が分からない
家事や育児の経験が少ない夫は「何をどうすればいいか分からない」と感じがちです。このため、妻に具体的に指示を求めることが多くなり、妻の負担が増すことがあるようです。
夫も「育児を手伝う」という意識を捨てて、自ら育児や家事の情報を調べたり、積極的に取り組む姿勢を持つように考え方をシフトチェンジできたりするとよいかもしれません。
また、ママの声として、夫には最初は簡単な役割を依頼するなど、協力しやすい環境を整えて、少しずつ育児参加できるようにしたという声もありました。
産後の妻の変化に戸惑っている
産後の女性はホルモンバランスの変化や育児疲れで感情が不安定になりやすくなります。夫がこの変化に戸惑い、距離を置くと、妻に「理解されていない」と感じさせてしまうことがあります。
子どもを守るために必死で育児をしている妻に対して「出産前の妻に戻ってほしい」と要求するのは火に油を注ぐかもしれません。妻の感情の変化を自然なものと受け入れ、寄り添う姿勢を持てるとよいでしょう。
夫婦の役割分担に対する理解不足
夫が「仕事=夫、家事育児=妻」と考え、役割分担についての認識が不足している場合、妻の負担が大きくなり、夫婦関係に亀裂が生じることがあるようです。
家事や育児は妻の役割ではなく、夫婦で協力して行なうものという意識を持つことが大切でしょう。具体的な分担を話し合い、家庭での役割を明確にすることで、お互いの負担を軽減しましょう。
また、将来的に育児と仕事を両立させたいと考えている妻であれば、今後のキャリアについてもサポートするという姿勢を夫が見せることも、産後クライシスを引き起こさないための一つの方法です。
産後クライシスになりやすい人が乗り越える方法

産後クライシスを防ぐための具体的な対策と乗り越える方法を、ママやパパの体験談から紹介します。
夫婦で話し合う
夫婦でコミュニケーションの時間をとり、家事・育児の分担や互いの気持ちを共有することで、産後クライシスを乗り越えられたというママの声もありました。
お互いに感謝の気持ちを伝える時間を作り、不満を溜め込まないというルールを作ったというママやパパの声も。習慣になるまではあえてルール化するのもポイントかもしれません。
自宅での話し合いは具体的なタスクの分担やスケジュールを調整する、子どもを預けて外で話すときはプライベート重視の感覚で話すようにすると、お互いの家庭内のバランスが整ったというパパの声もありました。
同じ境遇の夫婦と悩みを共有する
自分と同じ境遇の家庭の話を聞けると「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と気持ちが落ち着くことがありそうですね。悩みを周囲の人に打ち明けられると、心のもやもやがスッキリして、リフレッシュにもなるでしょう。
同じ境遇の夫婦と交流し、悩みや体験を共有することで、孤独感を和らげることができます。ほかの家庭の話を聞くことで、自分たちの状況を前向きに捉えられるようになる場合もあるようです。
地域の育児サークルやオンラインコミュニティを活用して、新しいつながりを築いたことで、悩みを相談できたというママの声もありました。
ベビーシッターなどのサービスを利用する
家事や育児サービスの利用について「料金が高い」「活用するのは贅沢」と考えるママやパパもいるかもしれません。
ただ、なかには安価な値段でサービスを利用できたり、産後クライシスを回避することができて結果的にお得だったと感じたりするママやパパも多いようです。予算にあわせてそれぞれの家庭にあうベビーシッターサービスを利用してみるとよいですね。
信頼できるプロの力を借りることで、育児中の心と身体に余裕が生まれ、夫婦間のストレスも軽減されたという声も多くありました。
「自分たちで全部やらなければ」と考えず、必要に応じてサポートを取り入れることで、家庭の調和を保つことができそうです。
産後クライシスになりやすい人は夫婦で協力を
 nekokawaodori / stock.adobe.com
nekokawaodori / stock.adobe.com
「もしかしたら今の状況って産後クライシスかも…」と夫婦の関係に不安を抱く方もいるでしょう。産後クライシスは、出産後の生活環境の変化やホルモンバランスの乱れなどが原因で誰にでも起こりうる現象です。
産後クライシスになったときの対処方法は人それぞれのため、自分が納得のいく解決策を見つけられるとよいですね。
また、産後数年で状況が落ち着くといわれているようです。長い目で夫婦関係の修復に向けての話し合いやリフレッシュする時間を設けたり、ベビーシッターなどを活用してリフレッシュしながら夫婦で協力してのりきっていけるとよいですね。
産後クライシスになりやすいと感じたらキズナシッターを活用しよう
産後クライシスで悩みを抱え「子どもを預けてストレス解消したい」と願っているママや「育児疲れの妻に笑顔になってもらいたい」と考えるパパは多いようです。
そんなときは、ママが少し子育てを休む時間を作るために「キズナシッター」のご利用を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターの登録シッターは100%が保育士・幼稚園教諭・看護師のいずれかの資格を持つ保育のプロフェッショナルばかりです。
なかにはベテラン保育士や助産師経験があるシッターも在籍しているため、0歳児〜12歳児まで安心して預けられます。乳幼児のお世話で疲れた産後のママの気持ちもしっかりくみ取ってくれそうです。
専用のアプリやウェブサイトでは、希望条件や依頼したい日時で簡単にシッターを検索することができ、カスタマーサポートを利用すれば、条件に合うベビーシッターを無料で案内してもらうこともできます。
会員登録からシッター検索、予約、利用料金の支払いまでがすべてアプリやウェブで完結するため、忙しいワーキングマザーや共働き家庭でも気軽に利用できますね。
パパからの登録も多数!キズナシッターの無料会員登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらKIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。