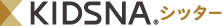「子どもの預け先がない」を解決!仕事と両立できる選択肢とパートなどの柔軟な働き方

子どもの日常的な預け先
 Kot63 / stock.adobe.com
Kot63 / stock.adobe.com
子どもが体調不良のときや長期休暇中、預け先に困るママやパパは多いですよね。これは、日常的に利用している施設が、そうした期間に休園・休所になるケースが多いからでしょう。
まずは、仕事をしているママやパパが、普段は子どもをどこに預けているのか聞いてみました。
幼稚園、小学校
共働き家庭の増加に伴い、預かり保育を実施している幼稚園も増えていることから、仕事をしているママも幼稚園を利用しやすくなっているようです。パートを始めるママのなかには、子どもの年齢に応じて社会復帰を考える方もいました。
保育園や学童
パートやフルタイムといった働き方に関わらず、仕事の勤務時間に応じて、保育園や学童を利用しているママもいるようです。共働き家庭が増えてきているからか、早めに申し込まないと保育園の入園や学童が利用できないという声も聞かれました。仕事を始めるタイミングにあわせて、子どもの預け先を確保できるよう、早めに詳細を調べておくと安心かもしれません。
子どもの体調不良のときの預け先
 polkadot / stock.adobe.com
polkadot / stock.adobe.com
子どもは急な発熱や感染症にかかることも多く、対応に困っている家庭も少なくないのではないでしょうか。そのようなとき、仕事をしているママやパパたちは、どうしているのでしょうか。
子どもが体調不良のときの預け先について聞いてみました。
パートナー
仕事を何日も休むことが難しい場合に、パートナーと相談しながら対応している方もいるようです。パパは日頃の子どもの様子をわかっているので安心感があるという声もありました。
両親や義父母
近くに両親や義父母が住んでいて頼れる場合、子どもの預け先として気軽に相談できるというママやパパもいるかもしれません。なかには、両親に自宅へ来てもらい、子どもを見てもらうという方もいました。
病児保育・病後児保育
地域によっては、病気の療養中や回復期にある子どもを一時的にお願いすることができる施設があるようです。なかには、病気の初期に子どもを預けられる病児保育を利用したことがあるという声も聞かれました。どちらも利用する場合には、事前登録が必要なため、早めに確認しておきましょう。
病児保育対応のベビーシッター
自宅で個別保育してもらえるベビーシッターサービスのなかには、病児保育に対応しているところもあるようです。これからサービスを検討する場合は、子どもが体調を崩したときを見据えて、病児保育対応かどうかについてもしっかり確認しておくと安心かもしれません。
キズナシッターでは、病児後含む病児保育にも対応しています。詳しくは以下の記事をご確認ください。
ファミリー・サポート・センター
病児保育に対応しているファミリー・サポート・センターは、急な子どもの体調不良時に、保護者の大きな支えとなってくれるかもしれません。自治体によって対応はさまざまなため、こちらも事前に確認しておきましょう。
子どもが長期休暇のときの預け先
 Maki_Japan / stock.adobe.com
Maki_Japan / stock.adobe.com
小学校や幼稚園では、夏休みや春休みなどの長期休みがあります。ここでは、そのような長期休みの際の子どもの預け先についてのママたちの声を紹介します。
両親や義父母
子どもの年齢に応じて、両親や義父母に泊まりでの預かりをお願いする家庭もあるようです。子どもにとって祖父母とすごす環境は、日常の生活とは違い、普段できないような経験が成長の機会にもなるかもしれません。
幼稚園や学童の預かり保育
長期休みの際には、幼稚園の預かり保育や学童保育を利用しているママもいるでしょう。パートをしているママのなかには、幼稚園選びの際に、預かり保育の有無について事前に調べ、参考にしている方もいました。預かり保育や学童の内容は、それぞれの施設によって異なるため、利用を検討する場合には早めに調べておくと安心かもしれません。
ショートステイ・トワイライトステイ
ショートステイとトワイライトステイは、どちらも子育て短期支援事業の一環として、保護者が一時的に子どもを養育できない場合に利用できるサービスです。ショートステイは宿泊を伴いますが、トワイライトステイは宿泊を必要としない場合に利用できます。どちらも、利用料金や対象年齢、受け入れ条件は自治体や施設によって異なるため、利用を検討する際には、あらかじめ自治体の詳細情報を確認するようにしましょう。
出典:子育て短期支援事業について/こども家庭庁自治体の放課後子ども教室・児童館
自治体によっては、小学校の校庭や教室などを利用して、子どもの遊び場を提供する事業が行われているようです。夏休みや春休みなどの長期休暇中も対応していることから、仕事をしているママやパパからは助かるといった声が多くありました。また、同様の取り組みを児童館で行っている場合もあるそうです。
民間学童
民間学童は、公立学童に比べて運営方針やプログラムに多様性があり、特定の分野に特化したサービスを提供しているところが多数存在するようです。英語やスポーツ、プログラミング、アートなど、子どもの好きな分野を伸ばせるよい機会になるかもしれません。
シーズンスクール・短期イベント
このようなシーズンスクールや短期イベントは、ただ預けるだけでなく、子どもの興味や才能を伸ばす貴重な機会といえそうです。半日や数日間といった短い期間で参加できるものが多く、費用も比較的抑えられるため、気軽に試せるのも魅力かもしれません。
ベビーシッター
ベビーシッターサービスは、長期休み中に子どもが慣れた環境で安心してすごせるだけでなく、保護者の多様なニーズにも柔軟に対応してくれる頼れる存在でしょう。ほかにも、急な予定変更にも柔軟に対応してもらえることが多く、安心して仕事を入れられるというパパの声もありました。
ファミリー・サポート・センター
ファミリー・サポート・センターは、顔見知りの協力会員の方に依頼できるため、子どもも親も安心できるのが魅力のひとつかもしれません。子どもの長期休み中に、学童保育が早く終わる日や習い事の送迎に手が回らないときなども助かっているという声がありました。
ママ友
近くに頼れる家族が住んでいない場合には、親しくしているママ友に依頼するという声も聞かれました。ママ友に依頼する場合、負担をかけてしまうことを考え、自分の都合がつくときには率先して預かりを申し出るようにしているという方もいました。
留守番
子どもがある程度大きくなると、長期休みなどは留守番をさせる家庭もあるようです。火を使うことがないようお弁当を用意しておいたり、定期的にビデオ通話などでコミュニケーションを取ったりして、子どもが安心してすごせるように事前に対応しているママもいました。
仕事の働き方で工夫できること
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
仕事をしているママやパパのなかには、体調不良時や長期休み中も子どもが不安なくすごせる環境を作るため、働き方を工夫している方もいるようです。どのように働き方を工夫しているのか、聞いてみました。
シフトの融通がききやすい仕事を選ぶ
これから仕事をしようと考えているなら、シフトの融通がききやすい仕事を選ぶこともひとつの方法かもしれません。最近では、勤務する時間や曜日などを自分で自由に設定できる職場もあり、子育て中でも働きやすい環境が増えてきているようです。
事前に長期休みなどを伝えておく
事前に長期休みの日程について職場に伝えておくことで、うまく対応してくれる場合もあるようです。パートの面接時に、子どもがいることや長期休みの対応について相談しておくことで働き方を工夫をしたという方もいました。
在宅など勤務スタイルを変更する
勤務内容によっては、在宅ワークなど勤務スタイルを一時的に変更するのもひとつの方法かもしれません。子どもの預け先を探したり子どもに寂しい思いをさせたりすることなく仕事を行うことができるため、助かっているという声も聞かれました。
複数の預け先を事前に考えておく
仕事を始めるタイミングで、子どもの預け先について家族で相談しておくことで、事前に両親や義父母に協力を仰いだり、もしものときのための対応を考えたりできるかもしれません。ベビーシッターサービスやファミリー・サポート・センターなどの利用には、事前登録が必要になってくるため、早めに詳細を確認しておくと安心かもしれません。
子どもの預け先で悩むママ・パパたちからよくある質問
 maroke / stock.adobe.com
maroke / stock.adobe.com
ここでは、子どもの預け先について悩むママやパパたちから寄せられる質問に答えます。いざというときのために事前準備をしっかり行い、子どもが安心してすごせるような環境づくりを目指しましょう。
Q1.保育園から急な呼び出しがあったとき、夫婦どちらも対応できない場合にほかに頼れる場所はある?
A.以下のようなサービスや事業を活用しましょう。
- ベビーシッターサービス
緊急時に対応可能なベビーシッター会社に登録しておくと、急な依頼にも対応してもらえる場合があります。 - ファミリー・サポート・センター
自治体が運営する会員制サービスで、育児の援助を受けたい人と行いたい人が会員となり、一時的な預かりや送迎などを依頼できます。 - 病児保育・病後児保育
提携している医療機関や施設で、病気の子どもを専門的に預かってくれます。事前の登録が必要な場合が多いです。
Q2.夏休みや春休みなどの長期休暇中、学童以外で安心して預けられる場所はある?
A.子どもの預け先は多岐にわたるため、子どもや保護者のニーズによって選べるとよいかもしれません。以下にいくつか紹介します。
- 短期預かりサービス(民間学童やキッズクラブなど)
民間の企業が運営する学童保育で、教育プログラムが充実していたり、長期休暇中に特化したコースを提供していたりする場合もあります。 - 児童館や公民館のイベント
長期休暇中に子ども向けのイベントを実施している場合があります。一時的な利用になることが多いですが、子どもの好奇心をくすぐるプログラムが用意されていることもあり、長期休暇中の貴重な体験となるかもしれません。 - 習い事のシーズンスクール
英語教室やスポーツクラブなどが集中プログラムを開催していることがあります。自分の得意分野を伸ばせる絶好の機会になるのではないでしょうか。 - 自治体の一時預かり事業
短時間・単発での利用ですが、自治体が提供する一時預かりサービスを利用できる場合もあります。
Q3.仕事の面接で子どもの急な体調不良や長期休みについて聞かれたら、どう答えるのが正解?
A.仕事の面接で子どもの預け先について聞かれた際は、以下の3点を意識して簡潔に伝えましょう。
- 具体的な対策を示す
病児保育の登録や民間学童サービスの利用、家族の協力など、具体的な預け先の確保やサポート体制を明確に伝える - 前向きな姿勢をアピールする
仕事と子育てを両立させるための工夫や、業務に支障が出ないよう努める責任感と働く意欲を示す - 事前の相談体制を伝える
万が一の際には、早めに職場に相談・連携を取り、円滑な業務遂行に努める旨を伝え、報連相の意識があることを示す
Q4.近くに頼れる身内がいない場合、どのようなサービスを利用できる?
A.身内が頼れない場合でも、子どもの預け先は複数あります。
自治体のファミリー・サポート・センターは安心して利用できるうえ、比較的安価な点で多くの保護者の方に受け入れられています。自宅に来てくれるベビーシッターサービスは子どもの環境変化が少なく、柔軟に利用できることが魅力のひとつでしょう。地域の保育園や認定こども園の一時預かり事業、地域のNPOや民間の子育て支援サービスも検討してみてはいかがでしょう。
Q5.幼稚園児でも利用できる、長時間預けられる場所はある?
A.幼稚園の預かり保育だけでは勤務時間に間に合わないという家庭も多いでしょう。その場合は、自宅で子どもを預かるベビーシッターサービスを検討してみましょう。幼稚園への送迎から帰宅後の長時間保育まで柔軟に対応しており、手厚いサービスが期待できます。
ほかにも、幼児クラスを設けている民間学童やキッズクラブのなかには、幼稚園の終了時刻に合わせて園まで迎えに行き、その後施設で長時間預かるサービスを提供しているところがあります。
Q6.子どもが病み上がりで保育園に登園できないときの預け先はある?
A.自治体によっては、病気の回復期で集団保育が難しい子どもを専門に預かる施設「病児後保育」があります。なかには、病児保育に対応しているベビーシッターサービスやファミリー・サポート・センターもあるようです。どれも事前登録が必要な場合がほとんどなため、時間があるときに必要な準備をしっかり行っておきましょう。
「子どもの預け先がない!」となる前に対応策を考えておこう
今回は、共働き家庭にとって悩みのひとつである、子どもの預け先や働き方の工夫について体験談を交えて紹介しました。
子どもの預け先は、それぞれのシーンやライフスタイル、家庭のニーズによって選択肢も異なるかもしれません。状況にあわせて、子どもが安心できる方法を考えられるとよいでしょう。また場合によっては、家庭との両立を考え、パートで無理のない働き方を選んだり、事前に職場に理解を求めたりしておくことも必要かもしれません。
子どもの急な体調不良や長期休みなどで預け先に悩んでいる場合は、地域のサポート事業やベビーシッターサービス、民間学童などを利用して、周囲からの協力を得ながら対応できるとよいかもしれませんね。
保育のプロがシッティング「キズナシッター」の活用も
長期休み中や体調不良時の子どもの預け先に悩んだ際には、保育のプロがシッティングを行う「キズナシッター」を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターに登録しているベビーシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師など全員が国家資格所有者です。そのため、専門知識をきちんと学び、保育現場などでの経験豊富なベビーシッターが多いのが特徴です。
担当するベビーシッターは利用者自身が希望に合わせて探すことができ、悩んだ場合には、無料のカスタマーサポートを活用することも可能です。入会費や年会費はかからず、利用した分のみの支払いとなる点も魅力のひとつでしょう。
いざというときのために、専用アプリをダウンロードし、会員登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。