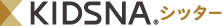看護等休暇とは。2025年法改正で育児と仕事はどう変わる?変更ポイントを徹底解説

看護等休暇とは
 kai / stock.adobe.com
kai / stock.adobe.com
「看護等休暇」とは、労働者の子どもが、病気やケガになったときに取得できる、育児・介護休業法で定められた法定休暇のことを指します。
2025年からは、この育児・介護休業法が改正され、「子の看護休暇」が「子の看護等休暇」へと名称を新たに、大幅に改正・拡大されます。
この改正では、対象となる子の範囲が小学校3年生修了までに引き上げられたり、取得事由に、学級閉鎖や入学式・卒園式への参加などが追加されたりします。また、より多くの保護者がこの制度を利用できるようになることも大きな変更点のひとつでしょう。
この記事では、今回の法改正のポイントをおさえながら、この変更点によって、子育て世帯の働き方や育児が具体的にどのように変わるのかについて、わかりやすく解説します。
まずは、看護等休暇の概要を以下に説明します。
看護等休暇の取得条件
勤務形態によっては、自分が看護等休暇を取得できるのかどうか不安な方もいるでしょう。
看護等休暇の対象者は、正社員に限らず、契約社員やパート・アルバイトも制度の対象となります。また、看護等休暇の取得は、事前に予測できないことから、当日でも取得可能です。そのため、電話での口頭による看護等休暇の取得申請が行え、必要な手続きや診断書の提出は、後日出社後に行うことが一般的のようです。
なお、共働きかどうかにかかわらず、配偶者が専業主婦(夫)であっても、看護等休暇を取得することは可能ですが、働き方によっては、看護等休暇の対象外となる場合もあるようです。この点は後述の「法改正ポイント」を確認しましょう。
看護等休暇の時間や給与の定め方
働くママやパパのなかには、看護等休暇が無給であることに不満を感じている方も少なくないようです。子どもの看病のために仕事を休んでも給与が発生しないため、取得に対して消極的になっている方もいるでしょう。
看護等休暇の時間や給与の定め方は、企業によってさまざまで、各企業が有給とするか無給とするかを判断します。無給の場合は、多くのママやパパが、有給休暇やほかの制度と組み合わせて対応しているのが現状のようです。
一方で、福利厚生の充実を目的として、独自に看護等休暇を有給にしている企業も存在します。特に、大企業や労働組合の影響が強い職場では、看護等休暇を特別有給休暇として認めるケースもあり、職場環境によって大きな差がみられるようです。
自分の勤務先が、看護等休暇が有給・無給かは、企業の就業規則に明記されているようです。取得を検討する際は、就業規定を確認することが必要でしょう。
出典:仕事と育児・介護の両立支援対策の充実について(案) 概要/厚生労働省看護等休暇を定めている法律の改正
 BillionPhotos.com / stock.adobe.com
BillionPhotos.com / stock.adobe.com
前述したように、看護等休暇は「育児・介護休業法」によって定められています。これは、子育てや介護をする労働者が、仕事との両立をしやすくするための法律です。
看護等休暇と似ている休暇制度として「介護休暇」が挙げられますが、この介護休暇も同様に、育児・介護休業制度で定められているものです。看護等休暇は、幼い子どもをもつ従業員が対象者であるのに対し、介護休暇の対象者は、要介護状態の家族がいる従業員という点が大きな違いでしょう。
このような介護を理由とする離職者の増加や、男性の育休取得率の低さなどが問題となっていることから、近年、性別や年齢に関係なく、育児・介護と仕事を両立するための法改正が行われています。
2025年法改正のポイント
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
ここでは、2025年4月1日から段階的に施行される、育児・介護休業法の改正ポイントを紹介します。
看護休暇の見直し
まず、子どもの看護休暇の内容が大幅に見直されました。この点について、以下に表でまとめました。

なお、取得可能日数は、1年間に5日、子が2人以上の場合は10日と、現行日数から変更はないようです。
残業が免除される人の拡大
施行前は、「3歳未満の子を養育する労働者」とされていましたが、今後は、「小学校就学前の子を養育する労働者」と、対象者の範囲が拡大されます。
育児のためのテレワーク導入
3歳未満の子どもを養育する労働者がテレワークを選択できるように、事業主に対して努力義務が課されます。
また、3歳未満の子を養育する労働者が、短時間勤務制度にて働くことが難しい場合も、代替措置として、テレワークが追加されます。
育児休業を取得した人の数を公表
これまでは、従業員数1,000人超の企業に、育児休業等の取得状況を公表することが義務づけられていましたが、今後は、従業員数300人超の企業へと、対象が拡大されます。
これにより、男性の育休取得率も徐々に上がっていくことが期待できるかもしれません。
以上4点においては、2025年4月1日に施行されますが、以下については、2025年10月1日に施行されます。
柔軟な働き方の実現
事業主は、3歳から小学校に入る前の子どもを育てている社員のために、以下の5つの選択肢のなかから2つ以上を選んで用意することとします。社員は、そのなかから1つを選んで利用することができますが、会社がどのサポートを用意するかは、労働組合などの意見を聞く必要があります。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇(養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
- 短時間勤務制度
なお、事業主は、3歳になる前の子どもを育てている社員一人ひとりに、働き方を柔軟にするためのこれらの制度を利用するかについて確認することが必須となります。
これらの選択によって、フルタイム勤務を諦めていた方も、柔軟に働けるようになることを期待したいですね。
働き方の個別相談
社員本人、または配偶者が妊娠・出産したときと、子どもが3歳になるまでの間に、事業主は、仕事と育児の両立に関して、その社員の希望を聞く必要があります。
たとえば、勤務時間帯や勤務地などを含め、どんな働き方がよいのかや、いつ育児のサポート制度を使いたいか、仕事の量や内容で困っていることなどを、面談や書類などで個別に確認します。
また、育児休業後の復帰時や労働者から申し出があった場合などでも、このようなコミュニケーションを取ることが望ましいとされています。
出典:育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法の2024(令和6)年改正ポイント/厚生労働省看護等休暇の改正で育児と仕事はどう変わる?
 wheeljack / stock.adobe.com
wheeljack / stock.adobe.com
以上のような法改正ポイントから、子育て世帯の働き方はどのように変わるのでしょうか。仕事と育児両方の側面から具体的な変更点をみていきましょう。
希望に応じた働き方が選べる
これまでは3歳以下の子どもを育てる労働者を対象に、一日の労働時間を6時間とする短時間勤務制度や、それに代わる措置を講じることが定められていました。
しかし法改正によって、従業員のさまざまなニーズに合わせて、労働時間や勤務地を柔軟に決めることが可能になりました。
たとえば、育児と両立するために短時間勤務が難しいと感じているママが、今後はテレワークや始業時刻の変更などを利用して勤務時間を十分に確保できるようになるかもしれません。転職して間もない方が、入社してすぐ看護等休暇を取得することも可能です。
このように、育児と仕事を両立するための支援制度を利用しやすい職場となり、個々のニーズに合う働き方の実現が期待されるでしょう。
子どもの年齢に応じて柔軟な働き方ができる
これまで残業など所定外労働の制限は「3歳以下の子どもをもつ労働者」が対象となっていましたが、今回の改正により「小学校入学前までの子どもをもつ親」に対象が拡大されました。
未就学児をもつ家庭では、体調不良など想定外のことが起こりやすく、残業しなければならない日に限って子どもの対応をしなければいけないというシーンも少なくないかもしれません。家庭だけでなく職場に対しても精神的なストレスを抱えがちなママやパパが、子どもの年齢に関係なく、気持ちよく働ける環境が整っていくとよいですね。
入学式などの行事に参加できる
一生に一度しかない子どもの行事に出席できるようになるのも、今回の法改正の大きな利点のひとつではないでしょうか。
子どもの体調不良とは違い、入学や卒園などの式典出席で会社を休むことに抵抗感がある方も少なくないでしょう。このように法律で定められることで、「申し訳ない」というネガティブな感情をもつことなく、堂々と子どもの晴れやかな一日に寄り添えるかもしれません。
誰もが育児と仕事を両立できるように
今回は、2025年4月1日から段階的に施行される看護等休暇の法改正について解説しました。
今回の法改正では、育児と仕事を両立する保護者が、子どもの年齢や取得事由、取得する時期、シーンなどに限らず、柔軟な働き方ができる制度が盛り込まれていることがわかりました。
またそれによって、子どもを理由に働くことを諦めていた方や、一方で仕事を理由に子どもに寄り添うことができなかった方も、育児と仕事を両立して、気持ちよく生活できるようになるかもしれません。
労働者が抱える家庭の事情はさまざまで、希望の働き方や育児・介護への向き合い方も異なるでしょう。これらを両立するための支援制度を利用しやすい職場となり、それぞれのニーズに合う働き方ができるとよいですね。
0歳から12歳の子どものサポートは「キズナシッター」へ
育児・介護休業法の法改正によって、育児と仕事により前向きになっている保護者の方も多いでしょう。
そのような方たちを「キズナシッター」も応援しています。
キズナシッターは、保育士や幼稚園教諭、看護師といった国家資格所有者のみが登録しているベビーシッターサービスです。0歳の赤ちゃんから12歳までの子どもを対象としています。当日の利用予約も可能なため、急ぎの仕事があるときや、ひとりで買い物に出かけたいときなども利用しやすいと好評です。
シッティングを依頼するベビーシッター選びで迷ったときは、コンシェルジュによる無料サポートにも対応しています。会員登録や年会費などの費用は一切かからないため、この機会にぜひキズナシッターの会員登録から始めてみてはいかがでしょうか。
スマホ版・ベビーシッターさん検索はこちら
Click!詳しくはこちらお住まいのエリアからシッターさん検索が可能です♪
※実際のご予約依頼はアプリからお願いします。
KIDSNAシッターのご利用方法


ご利用の流れ
KIDSNAシッターのアプリより、保護者さまとお子さまの情報を登録します。事務局で確認後、審査結果をメール通知します。審査が完了したらシッターへの依頼ができるようになります。

シッター探し
審査を待つ間にシッターを探しておきましょう。アプリの検索画面からご希望条件・日時を設定し絞込検索ができます。お気に入りのシッターをアプリ上で保存しておくこともできます。

面談依頼を送る
面談依頼を
送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)初めてのシッターとは1時間の面談を行い、お預かり内容や保育方針の確認をし、お子さまと慣れてもらいます。面談には1時間分の料金が発生します。面談依頼を送ると見積りが届くので、確認して依頼を確定します。
- 面談依頼を送るとメッセージのやりとりが可能になります。

シッティング依頼を送る
シッティング
依頼を送るシッターの
見積りを待つ見積りを承認
(依頼確定)面談依頼を送ったら、続いてシッティング依頼を送ることができます。シッターから見積もりが届いたら、内容を確認して依頼を確定します。

面談・シッティング当日
当日、シッターは5分~10分前を目安に到着するので、ご家庭のルール、お預かりの注意事項、鍵の扱い、緊急時の対応方法など必要事項をお伝えください。

完了後の決済/レビュー
面談・シッティング完了後、シッターからシッティング報告書が届きます。内容をご確認いただけましたら、決済ボタンを押してください。事前にご登録いただいたクレジットカードでのお支払いになります。
レビュー投稿にも是非ご協力ください。