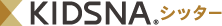子ども観とは。例えばどういうものをいう?大切にしたいことと活かせる職業

子ども観とは
 kimi / stock.adobe.com
kimi / stock.adobe.com
「子ども観」とは、子どもをどのような存在として捉えるのかという考え方のことを指すようです。これは、「絶対に〇〇であるべき」といったものではなく、子どもと関わる立場や職種に属する人の数だけ、多様なかたちがあると考えられています。
なお、子ども観と同じように、保育の現場では「保育観」という言葉も使われます。子ども観が、子どもをどのように捉えるかという見方であるのに対し、保育観は、子どもの成長や発達を促すために何を大切にしていくべきかという考え方を指すようです。
子ども観は、子どもと関わる仕事をするうえで非常に重要な視点でしょう。そこで今回は、子ども観を考える際に意識したいことについて掘り下げていきます。
子ども観の例
 taka / stock.adobe.com
taka / stock.adobe.com
子ども観にはさまざまな考え方がありますが、具体的にどのようなものをいうのでしょうか。
ここでは、代表的な子ども観の例をいくつか紹介します。
子どもは未熟で、守り導くべき存在である
この子ども観は、子どもを知識や経験がまだ不十分な存在として捉えているといえます。つまり、大人が子どもを危険から守り、社会のルールや規範を教えて正しい方向に導く役割を担うべきという考え方でしょう。
子どもが危険な場所に近づかせないようにする、ルールを教える、また、子どもが困っているときに手を差し伸べるというようなことも、この子ども観のひとつといえそうです。
子どもは自ら育つ力を持った、主体的な存在である
子どもは、生まれながらにして自ら成長しようとする力をもつという考え方でしょう。
具体的には、子どもが好奇心をもったことには失敗してもいいから挑戦させる、必要以上に手を貸さず自分で解決できるように見守るといったことがあるかもしれません。このような子ども観をもつ方は、子どもの興味や関心に寄り添い、主体的な遊びや学びを引き出す保育や教育を重要視するでしょう。
子どもは個性豊かで、一人ひとりを尊重すべき存在である
子どもを画一的な存在としてではなく、それぞれが独自の個性、性格、能力をもっている存在だという考え方は、多様性が重要視される現在の保育や教育のシーンにおいても活かされるかもしれません。
例えば、ほかの子と比べず、その子の得意なことや好きなことを見つけて、思いきり楽しめるような遊びや活動を提案することもそのひとつでしょう。子どもの個性を大切に育むことで、すべての子どもが安心して自分らしくいられることを目指す観点といえそうです。
子どもは大人とは違う、独自の文化を持った存在である
これは、子どもたちの遊びや言葉、価値観を大人の世界とは異なる、独自の文化として捉える子ども観でしょう。
子どもの遊びや行動を一方的に止めたり否定したりせず、「どうしてそれをしているの?」と子どもの気持ちを汲み取る考え方です。そうすることで、子どもたちの独自の文化に触れるなかで、新たな発見や学びを得る機会にもなるのではないでしょうか。
子どもと関わるうえで大切にしたいこと
 lielos / stock.adobe.com
lielos / stock.adobe.com
具体的な子ども観の例を紹介しましたが、自分の子ども観を捉えていくときには、実際の子どもの姿から学んでいくことが大切になるでしょう。
子どもと関わるうえで大切にしたいことをまとめました。
ありのままを受け止める
子ども観を考える際は、まず目の前にいる子どもの「ありのままを受け止めること」が大切だといわれています。
仕事を進めるなかで、自分自身の経験や価値観だけで子どものよい面や苦手な部分、対応方法などを探ってしまうことがあるかもしれません。しかしそれでは、自分自身の狭いものさしでしか子どもを見ていないことになってしまうでしょう。
目の前の子どもを知るためには、まずはありのままを受け止め、「何をしたいのか」「どんな気持ちなのか」模索していくことから始めましょう。
よく観察する
次に、「子どもを観察する」ことを意識していくとよいでしょう。しかし、ただ一方的に観察するだけでは、生きた子どもの姿や心の変化までを感じ取るのは難しいとされています。
観察するときは、子どもと行動をともにしながら心を通い合わせ、つながることが重要なようです。子どもを対象として見るのではなく、子どもが見ている世界を同じ視点で見たり感じたりすることで、はじめて子ども自身を知ることができるでしょう。
子どもに寄り添う
「子どもに寄り添う」ことを意識しましょう。子どものありのままを受け止め、心を通わせていくなかで、見えてきた子どもの願いや思いを、自身の子ども観につなげられるとよさそうです。
子どもの姿を捉えられるようになると、遊びや環境はどうあるべきか、どのようにサポートしていくべきかといったことなども見えてくるかもしれません。目の前の子どもに寄り添い、試行錯誤していくことが子どもの心に近づく一歩となるでしょう。
子ども観を活かせる職業
 ponta1414 / stock.adobe.com
ponta1414 / stock.adobe.com
子どもに関わることに興味をもち、実際に自分の仕事にしたいと考える方もいるようです。
ここでは、子ども観を活かせる職業について紹介します。
ベビーシッター
ベビーシッターは、保護者から依頼された場所に出向いて保育を行う仕事です。自宅でのシッティングが中心となるため、子どもの身の回りのお世話をしたり、遊び相手になったりすることが主な業務となるでしょう。
サービスによっては、保育園・幼稚園や習い事への送迎、宿題の手伝いなどをすることもあるようです。この仕事のやりがいは、一人ひとりの子どもとじっくり向き合い、その子の興味や関心に合わせたサポートを工夫することで成長を間近で感じられることといえそうです。
ベビーシッターの仕事は、子どもの自主性を尊重しながら、安全な環境で見守ることが重要なため、子どもが主体的な存在であるというような子ども観を持つ方に向いているかもしれません。また、子どもの興味や関心に合わせて遊びや活動を提供することから、一人ひとりを尊重すべきという子ども観も不可欠でしょう。
子どもの個性を理解し、その成長をサポートすることに喜びを感じる方にとって、ベビーシッターは大きなやりがいを感じられる仕事でしょう。
保育士
保育士は、0歳から小学校就学前の子どもの保育を行う仕事です。子どもたちの生活全般の世話をしながら、食事や排泄、衣服の着脱など基本的な生活習慣を身につけられるようサポートすることも大切な業務のひとつでしょう。
また、集団生活や遊びを通して社会性を身につけられるようサポートすることもあるため、子どもと密接に関わるなかで「昨日できなかったことをできるようになった」「興味のもったことを存分に楽しめていた」などと、子どもの成長を間近に感じられることがやりがいとなるでしょう。
保育園はさまざまな個性や背景をもつ子どもたちが集まる場所であり、集団生活のなかで多様な関わりが求められます。そのため、保育士に向いている子ども観は、ひとつに限定されないかもしれません。
しかし、子どもの興味を見守り、必要に応じてサポートする姿勢や、一人ひとりの個性に応じた関わりができる方は、保育士に向いているといえるでしょう。子どもたちと心を通わせ、サポートできることがモチベーションへとつながっていくのではないでしょうか。
幼稚園教諭
幼稚園教諭は、主に満3歳から小学校就学前の子どもの教育・保育を行います。保育園と同様に、遊びや集団生活のなかで、さまざまな学びをサポートすることが主な業務でしょう。
この仕事のやりがいは、運動会などの行事を子どもたちといっしょに作り上げ、成功させたときの達成感などが挙げられるでしょう。また、日々の心の交流が重要な幼児期の保育では、子どもたちと心を通わせられたと感じたときに、やりがいを見出すことも多いかもしれません。
幼稚園教諭も保育士同様、子どもを主体的な存在として捉え、一人ひとりの個性を尊重すべきだという子ども観をバランスよくもつことが重要だといえそうです。
小学校教諭
小学校教諭は、小学校に就学した子どもの教育を行います。国語や算数などの各教科を教える以外にも、ホームルームや給食など学校生活全般において指導やサポートをすることが、仕事の中心となるでしょう。
小学校生活は、社会生活を学ぶ大事な時期であるため、子ども一人ひとりの個性に寄り添いサポートする姿勢が重要だといえそうです。子どもたちの成長を感じ取ったり、クラスの担任として子どもたちといっしょに思い出を作り上げていったりすることは、自分自身の学びや成長を感じるきっかけにもなるかもしれません。
学童保育のスタッフ
学童保育のスタッフは、子どもが小学校の授業を終えたあとにすごす学童クラブなどの施設において、子どもたちをサポートする仕事です。近年では共働き家庭が増えていることから、学童クラブの存在は不可欠になってきているでしょう。
この仕事では、保護者が不在の間、子どもを安全に預かるという責任が伴います。そのため、社会のルールや安全を教えながら、子どもたちを正しい方向へ導くという意識が重要だといえそうです。
長い目で子どもの将来を支えていると感じられたり、働く保護者に必要とされていることを実感できたりすることも、大きなやりがいでしょう。
子ども観に関するよくある質問
子どもの成長に関わるなかで、「子どもは褒めて伸ばすべき?」「個性ってどこまで尊重すればいい?」など疑問は尽きないでしょう。
ここでは、子育てや教育に携わる方々からよく寄せられる、子ども観についての質問に答えます。
Q1.どのように、自分の子ども観を形成すればいい?
A.日々の保育や自分自身の子育てのなかで、子どもと真摯に向き合うことがもっとも重要でしょう。子どもの行動を観察し、その子の個性や興味、気持ちを理解しようと努めることで、自分の子ども観が自然と形成されるのではないでしょうか。
Q2.自分の子ども観が正しいのか不安です。
A.子ども観に、正しい・間違いはありません。大切なのは、自分自身の考え方を深く掘り下げ、なぜそう考えるのかを明確にすることです。ほかの人の考え方を知ることで、自分の子ども観をより豊かにすることもできるかもしれません。
Q3.保護者と自分の子ども観が違うときはどうすればいい?
A.まずは、保護者の子ども観を尊重し、耳を傾けることが大切です。そのうえで、なぜ自分はそのように子どもと関わっているのかをていねいに説明し、お互いの考えを共有する機会をもってみましょう。共通の目標を見つけることで、協力して子どもをサポートできるようになるかもしれません。
子ども観を意識して、子どもと向き合おう
子ども観とは、子どもをどのような存在として捉えるのかという考え方で、教育や保育、子育ての現場に関わる大人にとって非常に重要な観点です。
その一方で、「こうあるべき」というものではなく、さまざまなかたちがあることが特徴といえるでしょう。子ども観を考えるときには、まずは子どものありのままを受け止め、観察しながら寄り添うことを大切にしてみましょう。
子ども観を活かせる職業としては、保育士や小学校教諭、ベビーシッターなどが挙げられます。自分の子ども観を意識することで、ぴったりな職業を見つけられるかもしれません。子どもへの向き合い方に具体的な視点をもちながら、保育や教育をしていけるとよいですね。
自分の子ども観を大切にしながら「キズナシッター」で活躍しませんか
子ども観を意識して仕事をしたいと考えている方のなかには、「子ども一人ひとりに寄り添ってていねいに関わりたい」という方もいるようです。
そのように感じている場合は、「キズナシッター」での活動を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターは、ベビーシッターのマッチングサービスです。保育士や幼稚園教諭、看護師の資格を持っている方のみが登録できるため、資格を活かした働き方ができるのも魅力のひとつです。
働く時間は自分自身で設定できるため、自分のライフワークバランスを意識しながら仕事ができます。自身の子ども観を大切にしながらキズナシッターで理想の保育を実現しませんか。
ベビーシッターの登録はアプリから
面倒な手続きは一切不要!アプリをダウンロードしていただき、無料の登録説明会にご参加ください。