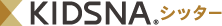子どもとの関わりで大切なこととは。意識するポイントや保育に活かせるアイデアと注意点

子どもとの関わりで大切なこと
 taka / stock.adobe.com
taka / stock.adobe.com
保育の仕事をしていくなかで「保育者として、子どもとどのように関わっていけばよいのだろう」と悩む方もいるかもしれません。子どもとの関わりで大切なことは、子どもの自己肯定感が育まれるように適切に対応していくことや、その過程において信頼関係を築くことだと考える方もいるようです。
では、具体的にどのように子どもと関わっていけばよいのでしょうか。子ども自身が自分らしく育っていけるような関わり方として、意識しておきたいポイントを紹介します。
ありのままの姿を認める
保育のなかで、子どもの行動によっては「どうしてこんなことをするのだろう」「どうして話を聞いてくれないのだろう」といった場合があるかもしれません。このようなときは、子どもの言動をありのままに受け止め、その心の奥にある思いを汲みとることから始めるとよいでしょう。
「〇〇がしたかったんだね」「〇〇な気持ちなのかな」というように、目の前にいる子どもが、自分の気持ちをわかってくれていると感じられるように言葉で伝えていくことも大切かもしれません。このような声かけをしながら気持ちに共感していくことで、子どもにとって保育者は安心でき信頼できる存在だと認識されるようになっていくでしょう。
子どもの姿を見守る
子どもが何に興味をもち、今何をしたいのか理解したうえであたたかく見守っていくことも、関わりを深めるための大切なポイントといえます。
たとえば、公園から帰らなければならないタイミングで、子どもが道脇のアリの行列から離れなくなってしまった。このようなときでも、焦らずに「アリさん長い行列を作っているね、アリさんもおうちに帰るのかな」と言葉をかけていっしょに観察する姿をみせると、満足した様子で自分から歩き始めてくれたという事例もあります。
これは、保育者が子どもの気持ちを代弁し、その姿勢を見守りゆっくり待つことで、子どもの「満足」を満たし、次への意欲を引き出していくことにつながったケースといえるでしょう。
どんなに小さな子どもにも、自分から興味をもって行動に移す力があることを信じ、常に見守る姿勢を大事にすることを忘れないようにしましょう。
心の変化を見つける
子どもには必ず、心が動く瞬間があるといわれているそうです。子どもと関わるなかで表情や行動から、「今〇〇に興味をもったかな」「〇〇がしたいのかな」と感じるときがあるかもしれません。そのようなときに、子ども自身の考え方や興味、行動など心が動いた瞬間を見逃さないことが保育者として大切となります。
変化があったタイミングで、適切にサポートしていくことが、保育者としてのよい関係構築へとつながっていくでしょう。
子どもの変化に合わせた仕掛けを作る
子どもの心が動いた瞬間を見つけたら、遊びや生活のなかで学びとなる仕掛けを作っていくと、より主体的に物事を楽しめるようになるかもしれません。
たとえば、子どもが虫などの生き物や自然に興味をもつようになったら、散歩先として自然散策ができるような場所を選んだり、すぐに調べられるように図鑑を用意したりするだけでも変化があるかもしれません。環境面の仕掛け以外にも、子どもの興味の先を見越して接し方を考えていくことも、仕掛けることのひとつといえるでしょう。
子どもの興味に合わせた仕掛けによって、子ども自身が遊びを工夫し、もっと楽しくしたい、上達したいという気持ちの芽生えにつながっていくと考えられています。このようなサポートは、探求心や意欲、感性など、目には見えないさまざまな育ちを育んでいくでしょう。
子どもと接するときに気をつけたい言葉がけや口調
 buritora / stock.adobe.com
buritora / stock.adobe.com
子どもと接する際は、言葉がけや口調も意識したいポイントでしょう。
子どもと関わるときに気をつけたい言葉がけや口調について、紹介します。
褒め言葉
子どもが何かできるようになったときに褒める際は、できた瞬間に「できたね」「よかったね」と、子ども自身のうれしい思いに共感していくことが大切でしょう。
「片づけを自分からできるようになってえらいね」など、具体的な内容を加えることで、子どもは「見ていてくれたんだ」という気持ちになり、よりうれしく感じられるかもしれません。また、「早くできた」「じょうずにできた」という結果よりも「最後まで諦めずに頑張ったね」というようにプロセスに重点をおくのもよさそうです。
うまくいかなかった場合でも、挑戦した勇気に目を向けていくことで、子ども自身の「次はもっとがんばろう」という意欲につながっていくでしょう。
注意を促す言葉
子どもと関わるなかで、危険な行動や人にケガをさせてしまうような場面があるかもしれません。そのようなときに子どもに注意を促す際は、危険な出来事があった瞬間に、わかりやすく短い言葉で伝えることが大切とされています。どうしていけないのかわかりやすく端的に伝えることで、子どもも理解しやすくなるでしょう。
また、子どもが生活するなかでは、失敗やうまくできないといった場面も少なくないでしょう。そのようなときに、子どもの失敗を恐れ、保育者が注意しすぎてしまうと自分から行動しにくくなってしまうかもしれません。
物事に対して注意深く対応する心や自分で考えて行動する心は、過去の経験や失敗から育まれていくと考えられています。周りの保育者が寛大な心で、子ども自身が挑戦した気持ちを大切にできるような言葉がけが行えると、子どもも安心して失敗から学んでいくことでしょう。
思いが伝わる口調
子どもとの関わりのなかで、思いが伝わるように穏やかな口調を意識することも大切なポイントとされています。
たとえば、子どもから積極的に行動してもらいたいときに、命令口調などの強引な言葉では子どもに伝わりにくいかもしれません。やさしい口調で、子どもの気持ちを汲み取りながら工夫していくとよさそうです。
子どもと接する際は、保育者自身が安定した気持ちで、明るい言葉を発することが大切でしょう。いつも心にゆとりを持ち、おだやかな気持ちで接していくことで、よりよい関係を築きやすくなっていくかもしれません。
年齢や性格に応じた遊びのアイデア
 Paylessimages / stock.adobe.com
Paylessimages / stock.adobe.com
子どもとの関わりで大切なことと、子どもへの言葉がけや口調において意識するポイントを押さえたら、それを日々の遊びのなかで実践していきましょう。
ここでは、それぞれの年齢や性格に応じた遊びのアイデアを紹介します。
0~2歳児(乳幼児)
この時期は、五感を刺激する遊びや安心感を得られる関わりを大切にしていきましょう。
たとえば、人見知りの子であれば、最初は無理に目を合わせず、近くで静かに絵本を読んだり、童謡を歌ったりするのもよいかもしれません。慣れてきたら、手の動きや声のトーンを変えながら、少しずつ体を動かす遊びに移行してみてはいかがでしょうか。
一方で、活発に動き回る子も多いかもしれません。このような子は、予想外の動きや音が好きな傾向にあるため、風船を浮かせて追いかけっこをしたり、積み木を高いタワーにして崩したりする遊びを取り入れてもよいでしょう。
3~5歳児(幼児)
幼児期になると、恥ずかしがりやな子や集中力がある子など、さまざまな個性がみられるようになるでしょう。また、想像力が豊かになる時期でもあるため、ごっこ遊びやルールの簡単な遊びで楽しむとよいかもしれません。
恥ずかしがりやの子には、ぬいぐるみやお人形を相手に、お医者さんごっこやお店屋さんごっこをしてみましょう。子どもが主役になれる場面を作ることで、安心して自己表現する機会を与えられそうです。
また、集中力がある子には、パズルやブロック、お絵描きなど、ひとつのことにじっくり取り組める遊びもよいでしょう。「このブロックで何を作ろうか?」「この色で何を描こう?」と質問することで、子どもの想像力をさらに引き出してみましょう。
6~8歳児(小学生)
小学生以上になると、知的探究心や協調性が芽生えはじめ、「やってみたい!」という気持ちが大きくなる時期かもしれません。このような気持ちを大切に、尊重してあげることを意識しましょう。
なかには、おとなしい子もいるかもしれません。そのような子には、カードゲームやボードゲームなど、相手との駆け引きを楽しめる遊びを提案してみてはいかがでしょう。勝敗にこだわりすぎず、かつ「どうやったら勝てるかな?」と戦略をいっしょに考えることで、コミュニケーションが深まるかもしれません。
一方で、リーダーシップのある子には、複数の遊びを組み合わせた宝探しや探偵ごっこなどもよさそうです。たとえば、子ども自身にルールを決めさせて、遊びをリードしてもらうことで、自己肯定感を高めることにつながるかもしれません。
【シーン別】子どもとの関わりのなかで困ったときの対応策
 polkadot / stock.adobe.com
polkadot / stock.adobe.com
子どもとの関わりのなかでは、喜びもあれば、どのような対応をしたらよいか分からなくなるような大変な場面に直面することもありますよね。
シーン別の対応策をまとめました。
癇癪
癇癪は、子どもがまだ自分の感情を言葉でうまく表現できないときに起こることが多いでしょう。まずは子どもの気持ちを受け止め、安心させてあげることが大切かもしれません。
子どもが感情的になっているときは、何を言っても耳に入りにくいかもしれません。まずは「大丈夫だよ」と寄り添い、感情の波が収まるのを待ちましょう。落ち着いてきたら、なぜ癇癪が起きたのかをいっしょに考え、「今度はこうしてみようか」と次の行動を提案してあげるのもよさそうです。
ケンカ
きょうだいや友だちとのケンカは、社会性を学ぶ大切な機会にもなり得ます。まずは双方の言い分を公平に聞いてあげることが大切でしょう。
このように、どちらか一方を責めるのではなく、まずはお互いの話を聞く姿勢を見せましょう。そして、「叩くのはいけないことだよ」と、行動の善悪を伝えたうえで、年齢によってはどうすれば仲良く遊べるかを子ども自身に考えさせることが重要かもしれません。
食べ物の好き嫌い
食べ物の好き嫌いは、子どもとの関わりのなかで多くの方が直面する課題のひとつかもしれません。食事の時間がお互いにとってストレスにならないよう、強制せずに工夫して対応しましょう。
「食べなさい!」と強く言うのではなく、ひと口だけ、半分だけなど、小さな目標を設定してあげるとよいかもしれません。また、食育活動として野菜の栽培をしたり、いっしょに食事の準備をしたりすることで、食べ物への興味が湧き、苦手意識が減ることもあるようです。
嘘やごまかし
子どもが嘘をつくのは、叱られることを恐れていたり、自分を守ろうとしたりする気持ちの表れかもしれません。まずは頭ごなしに怒らず、なぜ嘘をついたのか背景を理解しようと努めましょう。
子どもが嘘をついたときは、ただ叱るのではなく、正直に話す勇気を育むことが大切でしょう。「本当のことを話してくれてありがとう」と、正直さを評価することで、信頼関係を築くことにつながるかもしれません。
反抗期
「イヤイヤ期」とも呼ばれるこの時期は、自立心が芽生え、自分でやりたいという気持ちが強くなるため、何事にも反発することが増えるようです。
このように、子どもの「自分でやりたい!」という気持ちを頭ごなしに否定するのではなく、できる範囲で任せてみましょう。また、いくつかの選択肢を与えて、自分で決める機会を増やすことで、子どもの自立心を育むこともできるのではないでしょうか。
子どもとの関わり方を工夫しながら保育を楽しもう
子どもとの関わりで大切なことは、ありのままの姿を認めること以外にも、見守りながら心の変化を見つけ、その変化に合わせて仕掛けていくといった点が重要なようです。
また、子どもと接するときは、言葉がけも大切なポイントとされています。伝えたい内容に合わせて、子どもの気持ちに寄り添いながらやさしく伝えることを意識していくとよいでしょう。
子どもとの関わりで大切なことを理解し、日々の遊びや困ったときの対応に活かすことで、より強い信頼関係を築くことができるかもしれません。子どもとの関わり方を工夫しながら、保育を楽しんでいけるとよいですね。
「キズナシッター」で子ども一人ひとりとの関わりを大切に
子どもと関わる仕事がしたいと考えている方のなかには「一人ひとりとの関わりを大切にしたい」「保護者の思いを汲み取った保育をしていきたい」といった方もいるのではないでしょうか。
きめ細かな保育を大切にしたい場合には「キズナシッター」を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターとは、保育を必要としている保護者と、ベビーシッターをつなぐマッチングサービスです。キズナシッターとして働く場合は、保育士や幼稚園教諭、看護師といった資格が必須となるため、資格を活かした働き方ができるのも魅力のひとつでしょう。
シッティングの仕事は、自分のライフスタイルに合わせて最低1時間から自分で設定でき、その時間に応じたシッティング依頼を受けることができます。
子どもに寄り添った保育を実現していきたいと思ったときは、「キズナシッター」もひとつの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。
ベビーシッターの登録はアプリから
面倒な手続きは一切不要!アプリをダウンロードしていただき、スマートフォンやPCからおつなぎいただける無料のオンライン登録会にご参加ください。