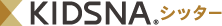ベビーシッターに必要な資格は?認定ベビーシッターなど民間資格の試験内容や取得方法を徹底解説

ベビーシッターになるには資格が必要?
出産後、仕事に復帰する母親が増え、また祖父母などと同居する家庭が減っている近年、子どもの預け先として注目を集めているのがベビーシッターです。月極のほか、週に数回、月に数回の一時利用も可能という柔軟性の高さや、子どもの送迎を考えなくてもいいことなどメリットは多く、心強い味方として毎日忙しい子育て世帯をサポートしています。
そんなベビーシッターという仕事について興味をもっている方も少なくないのではないでしょうか。今回は、ベビーシッターという仕事について、基本的なサービス内容や資格の必要性、ベビーシッターになる際に持っていると便利な資格などについてお伝えしていきます。
そもそもベビーシッターとはどんな仕事?
ベビーシッターとは、保護者がなんらかの事情で子どもを保育できないときに代わりに子どもを預かり、面倒を見てくれる人のことを意味します。ベビーシッターサービスの対象となるのは、主に0歳から12歳くらいまでの子どもです。ベビーシッターというと、”赤ちゃんの世話をする人”とイメージする方も多いかもしれませんが、実際には幅広い年齢を対象としていることが多いため、幼児から小学生を預かってほしいというニーズも少なくないようです。
サービス内容としては、保護者が留守中に、子どもの身の回りの世話をしたり、年齢が大きい子どもの場合はいっしょに遊んだり、宿題をみたりすることもあります。預かる時間はそれぞれのケースによりますが、おおむね3時間から多くて6時間程度の利用が中心のようです。
仕事としては、比較的時間の融通がききやすいため、ライフスタイルに合わせた働き方がしやすいでしょう。子どもの成長を感じることができたり、利用者のサポートができる仕事として「やりがい」を感じられたりすることも多いようです。
ベビーシッターに関する資格を取得する必要性
一般的にベビーシッターを目指す方は、子どもと関わることが好きな方や、子育て経験豊富な方のほか、保育士・幼稚園教諭・教員免許・看護師などの資格保持者などが多いようです。そのほかの資格として、公益社団法人全国保育サービス協会が認定する「認定ベビーシッター」がありますが、必ずしも必要なものではありません。
ですが、保育士や幼稚園教諭などの国家資格や免許を持たない方のなかには、専門の勉強をして、この認定ベビーシッター資格を取得してから働くというケースもあるようです。というのも、利用者から信頼を得てお子さんを預かったり子どもについて深く理解したりするためにも、ベビーシッターの資格を取得することは大きなメリットがあるからです。「認定ベビーシッター」などの資格を取得することで、よりベビーシッターの仕事について理解できたり、子どもを安全に世話したりすることにつながるようです。
資格をベビーシッターとして活かす方法
複数のベビーシッター民間資格、保育士や幼稚園教諭、教員免許、看護師などの資格保持者がベビーシッターとして活躍しているとお伝えしましたが、これらの資格や免許は実際にシッティングを行なう上でどのように活かせるのでしょうか。
保育士、幼稚園教諭、小学校教諭などは、保育や学習に関する知識を有していることから、保育業務にもそれらの専門的な知識を上手に活用できるでしょう。また、看護師の場合は、急な子どもの体調不良や怪我にも臨機応変に対応できるため、疾病をもつ子どもを抱える保護者も安心してシッティングを頼めそうです。そして助産師は、新生児の保育に関して専門的な知識を有しているという証明になり、この場合もまた保護者が安心して赤ちゃんを任せられるのではないでしょうか。
一方で、このような国家資格をもっている方のなかにも、ベビーシッターとして安定的に仕事を続けたいと考え、ベビーシッターに関する民間資格を取得する方もいるようです。このように幅広く資格を取得しておくことで、専門的な知識や技術を学ぶことができ、ベビーシッターの仕事に役立てることができます。もちろん、手当たり次第に資格を取得すればいいというわけではありませんが、ベビーシッターの仕事に活かせる資格は取得しておいて損することはないとも考えられます。自分にとって、どんな資格が必要なのかをしっかりと考え、役立てられる資格を取得することが大切かもしれません。
ベビーシッターに関する資格
 maru54 / stock.adobe.com
maru54 / stock.adobe.com
次に、ベビーシッターの仕事に活かせる資格についてひとつずつ詳しくみていきましょう。
まずは民間資格について紹介します。ベビーシッターに関する民間資格は複数あり、認定を行なう団体もさまざまです。基本的に、研修講座や通信講座で学び、試験に合格することで資格を取得する事ができます。ここでは、ベビーシッターに関する代表的な3つの民間資格を紹介するとともに、それぞれの団体が認定する資格の取り方と試験内容、取得にかかる費用についてまとめました。
また、ベビーシッターの求人のなかに、前述したような国家資格を持っていることを登録の条件としている派遣会社や事業者もあるため、これらの資格についてもあわせて紹介していきたいと思います。
公益社団法人全国保育サービス協会 「認定ベビーシッター」
「認定ベビーシッター」は公益社団法人全国保育サービス協会が認定する、ベビーシッターのための民間資格です。
ベビーシッターの業務として在宅保育や個別保育を行なうために、基礎的で専門的な知識や技術を身につけていることの証明になります。
取得している方のなかには、個別保育のスキルや専門性を向上させるために取得している方もいるようです。
資格の概要
公益社団法人全国保育サービス協会は、約30年とベビーシッター関連の協会としては長い歴史をもっている団体です。「認定ベビーシッター」資格では、専門知識や技術を取得するだけではなく、職業倫理を備えた実務経験ある人の育成を目指しています。
全国保育サービス協会では、近年多様な保育ニーズが求められているなかで、在宅保育サービスがより社会的に認知され、高い評価を得るためには、保育に関する知識や技術はもちろん、ベビーシッター独自の専門性を持つことが必要だと考えています。
そこで、「認定ベビーシッター」資格を付与することにより、ベビーシッターに対する信頼性を高め、ベビーシッター事業の向上とベビーシッターの社会的地位の確立を図ることを目的としているようです。
取得方法
資格をとるには、全国保育サービス協会主催の研修会への参加が必要です。研修会を修了すると認定試験の受験資格を得ることができ、その後、認定試験を経て審査が行なわれ、合格すると認定・登録となります。2024年度の認定試験は東京、大阪、名古屋にて実施されたようです。
認定試験では、選択問題40問と記述式(400字以内)1問が出題されます。内容はベビーシッターとしての基礎的知識・技術とともに、家庭訪問保育の特性及び専門性について、さらに、ベビーシッターとしての専門的知識及び技術について、全国保育サービス協会主催の研修の履修全般から出題されます。
取得にかかる費用は、16500円です。内訳は、認定試験の受験料が12100円、試験に合格した際の認定登録料が4400円です。
合格後は、認定ベビーシッターの「資格認定証」を受け取ることができます。また、初回の登録証には5年間の有効期限が定められています。更新には4400円かかるようです。この初回の更新後には有効期限がありませんので、一度更新すれば生涯使える資格となります。
出典:ベビーシッター資格認定試験のご案内 /公益社団法人全国保育サービス協会一般財団法人日本能力開発推進協会「ベビーシッター資格」
全国の保育施設でベビーシッターとして仕事をしたい方に推奨されている資格が、一般財団法人日本能力開発推進協会の「ベビーシッター資格」です。
子育てに関する基礎知識や年齢別育児ポイント、保育マインド、家族とのコミュニケーション、障害児保育、ベビーシッターの基本姿勢、こどもの病気の基礎知識、知育などの専門知識、保育実践力などを備えていることを証明する資格です。
資格の概要
一般財団法人日本能力開発推進協会は、医療事務や健康面のインストラクターなどさまざまな検定試験を実施している法人です。
この法人のベビーシッター資格の特徴は実務経験が必要ないことですが、障がい児保育や知育などについても触れ、家族とのコミュニケーションなど、ベビーシッターとして働く上で欠かせない知識を得ることができます。
取得方法
ベビーシッター資格の受験する条件として、まず協会が指定する認定教育機関が行なう教育訓練において、その全カリキュラムを修了する必要があります。
試験は、カリキュラム修了後、随時、在宅にて受験が可能となります。
試験内容は、子育てに関する基礎知識・年齢別育児ポイント・保育マインド・家族とのコミュニケーション・障がい児保育・ベビーシッターの基本姿勢・子どもの病気の基礎知識・知育といった学習内容から出題されます。
取得にかかる費用は、受験料5600円+受講料(講座は通信課程となり別途通信講座費用がかかる)となっています。
出典:ベビーシッター資格/一般財団法人日本能力開発推進協会一般財団法人日本医療教育財団「ベビーシッター技能認定」
財団法人日本医療教育財団は1974年に設立された団体で、医療や福祉に関わる複数の資格試験を実施しています。
2016年より職業能力の向上と子育て支援をめぐる社会的環境の向上に資することを目的に「ベビーシッター技能認定」を開始しました。
近年、家族構成の変化や働く親世代の増加により、多様な保育環境が求められるなかで、安心して子育てができる環境づくりを図っています。
資格の概要
この法人のベビーシッター資格は、施設や個人宅などで子育てを支援するベビーシッターに必要な知識および技能のレベルを評価、認定することによって、職業能力の向上と子育て支援をめぐる社会的環境の向上に資することを目的としています。
この資格を取得することで、ベビーシッターの基本知識をはじめ、子どもや子育て支援制度の概要など、子育て支援に関する基本的な知識と技能を身につけることができるといえるでしょう。
取得方法
このベビーシッター技能認定を受験するためには、まず承認を受けた教育機関で通信教育を受けることが必要です。財団が定めた所定の教育訓練ガイドラインに適合するカリキュラムで技能を習得し、教育機関の実施する修了試験に合格した方に技能が認定されます。
試験内容は「ベビーシッター技能認定申請資格に関する教育訓練ガイドライン 」より出題され、(1)子育て環境と支援(2)保育者の職業倫理(3)食事と栄養(4)小児保健(5)人間関係(6)ベビーシッターの基本の中から合計25問以上出題されます。
試験の解答時間は60分ですが、資料等の持ち込みが可能です。実務経験は必要ありません。
取得にかかる費用は、認定料3000円+講座料(通信課程となるため別途通信講座費用がかかる)となります。
出典:技能審査認定・ベビーシッター技能認定/一般財団法人日本医療教育財団保育士資格
次に、民間資格以外の資格をみていきましょう。
まずは、「保育士」です。一生ものの資格として人気があり、近年たびたび話題となる保育士不足の問題などから、需要がますます増加傾向にあります。もともと子どもが好きな方はもちろん、自身が親になって子育てをするなかで、保育士という仕事に興味をもつ方も多いようです。
資格の概要
保育士資格は、児童福祉法に基づき、厚生労働省が認定する国家資格です。
取得後は、保育所、児童養護施設、障がい児施設など、多岐にわたる児童福祉施設で働くことが可能です。
乳幼児期の保育は、子どもの人格形成に大きく影響するといわれており、たんに子どもが好きというだけでは保育士にはなれません。
子どもを預かり、けがや事故がないよう見守りながら長い時間を共にすごすのは、非常に責任の重い仕事といえます。そのためには保育についてきちんと学び、保育士の資格を取ることが重要になってくるかもしれません。
取得方法
4年制大学・短大・専門学校など、厚生労働大臣の指定する保育士養成施設を卒業し、取得するのが一般的となっています。
一方で、保育士養成施設を卒業しない場合は、年に2回実施される保育士の国家試験に合格する必要があります。毎年4万~5万人いる受験者に対して合格率は10%~20%台と狭き門になりますが、通信講座などで勉強し、取得する方もいるようです。
国家試験には8科目の筆記試験と実技試験があります。
なお、実技試験は筆記試験の8科目すべてに合格しないと受験することができません。しかし、筆記試験で一度合格した科目は3年間有効となるので、無理をせず数年かけて合格を目指すというのもひとつの方法かもしれません。
受験には、受験手数料の12700円が必要になります。
また、申請方法によって受験申請にかかる費用が異なります。受験の申請方法には、オンライン申請と郵送申請があり、郵送申請はオンライン申請よりも郵送料の観点から受験申請費用が高くなります。オンライン申請の場合、受験申請書を取り寄せる必要がなく、証明写真もスマートフォンで撮影してアップロードできるので、受験申請にかかる費用を抑えられるかもしれません。
なお、保育士試験に合格したあとは、登録料として4200円が必要となります。
出典:国家資格の試験実施主体、受験手数料、受験者数/厚生労働省幼稚園教諭免許
幼稚園教諭の仕事は、私立や公立の幼稚園に通う未就学児の子どもたちの教育を行なうことです。
それぞれの園の方針によってその内容は異なりますが、幼稚園教育要領に基づき作成したカリキュラムに沿って、日々の活動や教育が行なわれます。
園での行事の準備や片付け、教室内の装飾など、幼稚園教諭の仕事は多岐にわたります。
園児とすごす時間だけではなく、日々の活動や行事がスムーズに行なえるよう段取りを組むことも大事な仕事のようです。
保育士と同様、このような業務を行なうための専門的な知識は、実際にベビーシッターとして子どもをみるときも有利に働くのではないでしょうか。
資格の概要
幼稚園教諭免許は、幼児教育の専門家として、子どもの心身の発達を促し、社会性や基本的な生活習慣を身につけさせる役割を担います。
ひとつ前に紹介した保育士免許は厚生労働省の管轄となりますが、この幼稚園教諭は文部科学省が管轄しています。
そのため、小学校や中学校と同じようにひとつの教育機関として位置付けされているのが特徴です。
幼稚園教諭の主な役割は教育であり、学ぶことの楽しさを子どもたちに伝えていくことが目的とされています。
このように、保育士とはまったく別の目的や役割があることがこの免許の特徴かもしれません。
取得方法
幼稚園教諭養成課程のある4年制大学や短大、専門学校へ進み、幼児教育学や幼児心理学などの必要科目を履修することで、卒業と同時に取得することができます。
幼稚園教諭免許状には下記の3種類があります。
- 専修:大学院を卒業すると取得できる免許
- 1種:大学を卒業すると取得できる免許
- 2種:短大や専門学校を卒業すると取得できる免許
このように、取得までの学習時間に違いがあることは、将来性や待遇面への違いにつながるようです。
また、通信制大学でも所定の単位を取得することで、大学や短大などと同様に免許を取得することが可能です。
通学、通信においても教職課程を履修すれば国家試験を受ける必要がないということが特徴といえるでしょう。
また、保育士などで一定の勤務経験がある場合は、幼稚園教員資格認定試験を受けることができます。
この試験は、受験者の学力などが大学、または短期大学などで幼稚園教諭の二種免許状を取得したケースと同等の水準に達しているかどうかを判定するもので、この認定試験に合格し、都道府県教育委員会に申請すると、幼稚園教諭の二種免許状が授与されます。
受験資格は、
- 平成15年4月1日までに生まれていること
- 高等学校を卒業した者、その他大学(短期大学及び文部科学大臣の指定する教員養成機関を含む)に入学する資格を有する者であること
- 保育士(国家戦略特別区域限定保育士を含む)となる資格を有した後、所定の施設(幼保連携型認定こども園や認可保育所等)において、保育士等として3年以上かつ勤務時間の合計が4320時間以上あること
とされています。
出典:令和5年度 幼稚園教員資格認定試験 受験案内/独立行政法人教職員支援機構看護師免許
生まれたての赤ちゃんから、寿命を全うしようとしている高齢者まで、幅広い年代の患者に向き合い、医師のサポートを行ないながら、人々の健康を守るのが「看護師」です。
病児や疾患のある子どもを預けるときにも、看護師免許をもつベビーシッターであれば、保護者も安心して依頼できそうです。
資格の概要
病院のみならず、高齢者介護施設や訪問介護サービス、保健所や保育園・幼稚園などの公的機関、さらに企業などでも、看護師は必要とされる仕事です。
看護師国家試験の受験者数は毎年5万~6万人で、合格率は90%前後で高い水準で推移しています。
看護師国家試験の内容は、厚生労働省によって取りまとめられる「保健師助産師看護師国家試験出題基準」に沿って作成されますが、出題基準は4年に1度改定されるようです。
取得方法
国家資格である看護師資格を取得するには、文部科学大臣指定の学校もしくは厚生労働大臣指定の看護師養成所を卒業し、年に1回実施される看護師国家試験に合格しなくてはなりません。
学校は、4年制大学、3年制の短大・専門学校があります。これらの看護師を養成する教育機関では、厚生労働省と文部科学省から指定された教育カリキュラムを満たすことが求められています。
学ぶことは主に2つに分かれ、1つ目は人と関わる仕事を行なう上で必要な人間や環境、社会の仕組みを理解する基礎分野、2つ目は基礎看護学や臨地実習など看護師になるために必要不可欠な専門分野とされています。
また、教育機関によっては保健師・助産師の教育プログラムがあり、条件を満たせば看護師に加えて保健師・助産師の国家試験資格を得ることができるようです。
自分に合ったベビーシッター資格を取得し、個別保育について学んでみよう
 siro46 / stock.adobe.com
siro46 / stock.adobe.com
民間資格である「ベビーシッター」資格について、認定ベビーシッターをはじめ、3つの団体を中心に、取得方法、試験内容、取得にかかる費用について紹介しました。
また、民間資格以外の国家資格や免許についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。どの資格もまた、ベビーシッターを行なう上で非常に役に立つものといえます。
ベビーシッターに関する資格にはそれぞれ違いがあるため、資格取得を目指すときには一つひとつ特徴をつかむことが大切でしょう。自分に合った資格を選び、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
資格を通して個別保育について詳しく学ぶことが、ベビーシッターへの第一歩になるかもしれません。
保育士・幼稚園教諭・看護師といった国家資格の所有者のみが登録できる「キズナシッター」
保育士や幼稚園の資格をもっている方や、これから資格取得を目指す方のなかには「資格を活かした働き方がしたい」「ベビーシッターの仕事に興味がある」といった方もいるかもしれません。
資格を活かした柔軟な働き方や、ベビーシッターの仕事を探している場合には「キズナシッター」を検討してみてはいかがでしょうか。
キズナシッターとは、保育士や幼稚園教諭、看護師といった国家資格の所有者のみが登録できる、ベビーシッターと利用者をつなぐマッチングサービスです。
業務時間は自分で1時間から設定でき、その時間に応じて利用者の依頼が入るといったしくみになっています。
時間の融通がききやすくライフスタイルに合わせて仕事が行なえると、登録しているベビーシッターの方からも好評をいただいています。
収入面においては、時給1600円からで、こちらも自分で金額の設定が可能。
働き方によっては、高収入も期待できます。安心して仕事が行なえるよう、シッティング中の万が一のケガや事故に備え保険にも加入しています。
資格や経験を活かし、子どもに寄り添いながら「楽しかった」と思ってもらえるような個別保育を実現してみませんか。
ベビーシッターの登録はアプリから
面倒な手続きは一切不要!
アプリをダウンロードしていただき、無料の登録説明会にご参加ください。